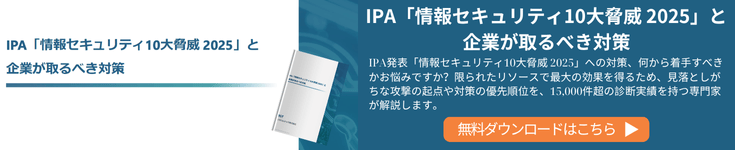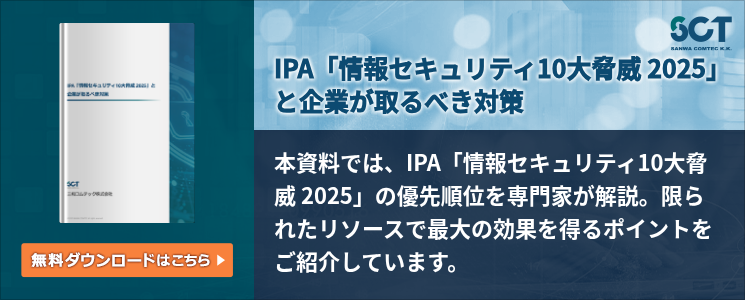企業の規模や業種を問わず、あらゆる組織がサイバー攻撃の標的となる現代。ひとたび攻撃を受ければ、事業停止や多額の損害賠償、そして社会的信用の失墜といった深刻な事態を招きかねません。もはやサイバー攻撃対策は、他人事ではなく、すべてのビジネスパーソンが知っておくべき必須知識と言えるでしょう。本記事では、サイバー攻撃の全体像を掴んでいただくため、その目的や多様な手口、実際に起きた被害事例、そして企業が講じるべき具体的な対策まで、最新情報を交えながら網羅的に解説します。
この記事でわかること
- サイバー攻撃とは何か、その目的や歴史といった基礎知識
- ランサムウェアや標的型攻撃など、最新の手口とその種類
- 国内外の企業で実際に起きた被害事例
- 企業が明日から実践できる具体的なセキュリティ対策
- IPAの発表に基づくサイバー攻撃の最新動向
巧妙化・多様化するサイバー攻撃から自社を守るためには、技術的な対策だけでは不十分です。サイバー攻撃への備えは、情報システム部門だけの問題ではありません。経営層から従業員一人ひとりまで、組織全体で取り組むべき重要な経営課題です。この記事を参考に、自社のセキュリティ体制を見直し、巧妙化する脅威から大切な情報資産を守るための一歩を踏み出しましょう。
サイバー攻撃の基礎知識
現代のビジネスや社会インフラはデジタル技術と密接に結びついており、サイバー攻撃はあらゆる組織にとって避けて通れない重大な経営リスクとなっています。被害を未然に防ぎ、インシデント発生時に適切に対応するためには、まずサイバー攻撃がどのようなものかを正しく理解することが第一歩です。この章では、サイバー攻撃の基本的な定義から、その歴史、そして攻撃者の多様な目的までを掘り下げて解説します。
サイバー攻撃とは?その定義と歴史
サイバー攻撃とは、コンピューターシステム、ネットワーク、または個人が利用するデバイスに対し、不正なアクセスや悪意のあるコードを用いて、データの窃取、改ざん、破壊、システムの停止といった損害を与える行為の総称です。 総務省では、サイバー攻撃によって引き起こされる脅威を「情報の機密性(Confidentiality)」「完全性(Integrity)」「可用性(Availability)」の3つの側面から定義しており、これらのいずれかが損なわれることで、個人や組織に深刻な被害をもたらします。
サイバー攻撃の歴史は、コンピューターとネットワークの発展と共に進化してきました。その変遷を理解することは、現在の脅威を把握する上で非常に重要です。
| 年代 | 主な特徴と出来事 |
|---|---|
| 1970年代~1980年代 | 黎明期:ネットワークの学術利用が主であり、攻撃は愉快犯的なものが多かった。1988年には、インターネットの規模を計測する目的で作成されたプログラムが意図せず大規模な障害を引き起こした「モリスワーム事件」が発生し、サイバーセキュリティの重要性が初めて広く認識されました。 |
| 1990年代~2000年代初頭 | インターネット普及期:Windows 95の登場などでインターネットが一般家庭に普及。それに伴い、「Melissa」や「ILOVEYOU」といったメールを介して感染を広げるコンピューターウイルスが世界的に流行しました。 |
| 2000年代中盤~2010年代 | 組織犯罪化・高度化の時代:攻撃の目的が愉快犯から金銭目的へと大きくシフトしました。 情報を盗むためのスパイウェアや、特定の組織を狙い撃ちにする標的型攻撃が出現。また、ボットネットを利用した大規模なDDoS攻撃なども見られるようになりました。 |
| 2020年代~現在 | 国家関与とサプライチェーン攻撃の時代:国家が背後にあるとされる高度な攻撃グループ(APT)による、重要インフラや先端技術を狙った攻撃が深刻化。 また、セキュリティ対策が手薄な取引先を経由して標的企業に侵入する「サプライチェーン攻撃」や、AIを悪用した巧妙な攻撃など、手口はより一層複雑化・巧妙化しています。 |
このように、サイバー攻撃は時代と共にその姿を変え、私たちの生活やビジネスに大きな影響を与え続けています。最新の攻撃動向を理解し、対策を講じることが、すべての組織にとって不可欠です。サイバー攻撃の全体像や具体的な対策については、網羅的に解説した資料「三和コムテック Security Solution Book」もご用意していますので、ぜひご活用ください。
攻撃者の正体は誰?その多様な目的を解明
サイバー攻撃と一言で言っても、その背後にいる攻撃者の姿や動機は一様ではありません。「誰が」「何のために」攻撃を仕掛けてくるのかを理解することは、効果的なセキュリティ対策を講じる上で極めて重要です。攻撃者は主に、その目的によって以下の3つのタイプに大別されます。
金銭目的のサイバー犯罪者
現在のサイバー攻撃の大部分は、金銭的な利益を直接の目的とするサイバー犯罪者によって実行されています。 彼らは個人であることもあれば、高度に組織化された犯罪グループである場合もあります。その手口は多岐にわたります。
- ランサムウェア攻撃:企業のデータを暗号化し、復旧と引き換えに高額な身代金を要求します。
- 個人情報・認証情報の窃取と売買:盗み出したクレジットカード情報やアカウント情報をダークウェブなどで売買し、利益を得ます。
- ビジネスメール詐欺(BEC):経営者や取引先になりすまして偽の送金指示を送り、多額の金銭をだまし取ります。
- 不正送金:ネットバンキング利用者の認証情報を盗み、預金を不正に送金します。
近年では、「Ransomware as a Service(RaaS)」のように、サイバー攻撃の手法がサービスとして提供されるケースも増えており、高度な技術を持たない犯罪者でも容易に攻撃を実行できる環境が整いつつあります。
政治・思想目的のハクティビスト
「ハクティビスト(Hacktivist)」とは、「ハック(Hack)」と「活動家(Activist)」を組み合わせた造語で、自らの政治的・社会的な主張やイデオロギーを実現するためにサイバー攻撃を行う個人や集団を指します。 彼らの目的は金銭ではなく、特定の政府や企業、団体への抗議活動や、自らのメッセージを社会に広く知らしめることです。
主な攻撃手法としては、Webサイトの改ざん(Defacement)、抗議のためのDDoS攻撃によるサービス停止、内部告発情報の暴露(リーク)などが挙げられます。国際的なハクティビスト集団である「アノニマス」や、内部告発サイト「ウィキリークス」の活動は、その代表例として広く知られています。
国家が関与するサイバーテロ
国家が背後で支援、あるいは直接的に実行するサイバー攻撃は、最も高度で深刻な脅威の一つです。 これらの攻撃は、単なる犯罪行為を超え、国家間の諜報活動、軍事作戦、政治的・経済的な優位性の確保といった戦略的な目的を持って実行されます。 攻撃対象は、政府機関や軍事施設だけでなく、電力、金融、交通、医療といった国民生活に不可欠な重要インフラにまで及びます。
国家が関与する攻撃は、特定の標的に対して長期間にわたり潜伏し、執拗に攻撃を続けることから「APT(Advanced Persistent Threat:高度で持続的な脅威)」とも呼ばれます。彼らはゼロデイ脆弱性(未公開の脆弱性)を悪用するなど、極めて高度な技術力を持ち、その活動が社会に与える影響は計り知れません。このような攻撃は、時に「サイバーテロ」とも呼ばれ、国家の安全保障を揺るがす重大な脅威として認識されています。
【手口別】サイバー攻撃の種類一覧
サイバー攻撃には、攻撃者が用いる手口や標的によって多種多様な種類が存在します。自社の情報資産を守るためには、まずどのような攻撃手法があるのかを理解することが第一歩です。ここでは、代表的なサイバー攻撃をカテゴリ別に分類し、それぞれの特徴や仕組みを詳しく解説します。
マルウェアを利用した攻撃にはどんなものがある?
マルウェア(Malicious Software)とは、デバイスやシステムに不利益をもたらす目的で作成された悪意のあるソフトウェアやコードの総称です。メールの添付ファイルや不正なWebサイトなどを通じて侵入し、情報の窃取やシステムの破壊など、様々な被害を引き起こします。
ランサムウェア
ランサムウェアは、感染したコンピュータ内のファイルやシステム全体を暗号化し、その復号と引き換えに身代金(Ransom)を要求するマルウェアの一種です。近年、企業にとって最も深刻な脅威の一つであり、一度感染すると事業継続に甚大な影響を及ぼす可能性があります。攻撃者は身代金の支払いを強要するだけでなく、支払いに応じない場合は窃取した情報を公開すると脅す「二重恐喝(ダブルエクストーション)」の手口も用います。
Emotet(エモテット)
Emotetは、主にメールの添付ファイルを通じて感染を広げるマルウェアです。 特徴的なのは、過去に実際にやり取りされたメールの内容を引用して返信を装うなど、受信者が信用しやすい巧妙な手口を用いる点です。 Emotet自体が情報を窃取するだけでなく、感染したPCにランサムウェアなど他のさらに強力なマルウェアをダウンロードさせる「ダウンローダー」としての役割も担うため、非常に危険視されています。
スパイウェア
スパイウェアは、ユーザーが気づかないうちにPCにインストールされ、個人情報や行動履歴などを収集して外部に送信するマルウェアです。 例えば、キーボードの入力履歴を記録する「キーロガー」によってIDやパスワード、クレジットカード情報が盗まれたり、Webサイトの閲覧履歴が収集されてマーケティングに悪用されたりします。 無料のソフトウェアをインストールした際に、同時にインストールされてしまうケースが多く見られます。
ウイルス・ワーム・トロイの木馬
これらは古くから知られるマルウェアの代表格ですが、それぞれに異なる特徴があります。違いを理解しておくことが対策の第一歩となります。
| 種類 | 特徴 | 主な感染経路 |
|---|---|---|
| ウイルス | ファイルに寄生(添付)して存在し、そのファイルが開かれることで活動を開始する。自己増殖能力を持つが、単体では存在できない。 | メールの添付ファイル、不正なWebサイトからのダウンロード |
| ワーム | 単独で存在でき、ネットワークなどを介して自己増殖しながら感染を拡大させる。 感染力が非常に高いのが特徴。 | ネットワークの脆弱性、メール、USBメモリ |
| トロイの木馬 | 一見無害なソフトウェアを装ってPCに侵入し、攻撃者の指示で内部から情報を盗んだり、システムを破壊したりする。自己増殖はしない。 | 信頼できる送信元を装ったメール、ソフトウェアのダウンロード |
ネットワークやサーバーを狙う攻撃
企業の活動に不可欠なネットワークやサーバーの機能を停止させたり、通信を妨害したりすることを目的とした攻撃です。
DoS/DDoS攻撃
DoS(Denial of Service)攻撃は、標的のサーバーに対して大量の処理要求やデータを送りつけ、過剰な負荷をかけることでサービスを停止に追い込む攻撃です。さらに、この攻撃を多数のPCから一斉に行うのがDDoS(Distributed Denial of Service)攻撃、すなわち分散型サービス妨害攻撃です。マルウェアに感染させて乗っ取った多数のPC(ボットネット)を踏み台にして行われるため、攻撃元の特定が困難です。
中間者攻撃
中間者攻撃(Man-in-the-Middle Attack)は、通信を行っている二者間に攻撃者が割り込み、送受信されるデータを盗聴、改ざんする攻撃です。暗号化されていない公衆Wi-Fiの利用時などに特に注意が必要です。利用者は正規のサイトにアクセスしているつもりでも、実際には攻撃者が用意した偽のアクセスポイントを経由して通信させられ、入力したIDやパスワード、個人情報が盗まれてしまいます。
ブルートフォース攻撃
ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃)は、特定のIDに対して考えられるすべてのパスワードの組み合わせを機械的に試行し、不正ログインを試みる手法です。「password」や「123456」のような単純なパスワードは、この攻撃によって短時間で破られてしまいます。近年では、他のサービスから漏洩したIDとパスワードのリストを用いてログインを試みる「パスワードリスト攻撃」も増加しており、パスワードの使い回しは非常に危険です。
Webアプリケーションの脆弱性を悪用する攻撃とは?
多くの企業がWebサイトやWebサービスを運営する現代において、そのプログラム上の欠陥である「脆弱性」を狙った攻撃は後を絶ちません。
SQLインジェクション
SQLインジェクションは、Webアプリケーションの入力フォームなどに、データベースを操作するための不正なSQL文を注入(inject)することで、データベースを不正に操作する攻撃です。 この攻撃が成功すると、データベースに格納されている顧客情報や個人情報が大量に漏洩したり、データが改ざん・削除されたりする可能性があります。
クロスサイトスクリプティング(XSS)
クロスサイトスクリプティング(XSS)は、脆弱性のあるWebサイトの入力フォームなどを通じて悪意のあるスクリプトを埋め込み、サイトを訪れた他のユーザーのブラウザ上で実行させる攻撃です。 これにより、ユーザーのCookie情報(セッションIDなど)が盗まれアカウントが乗っ取られたり、偽の入力フォームが表示されて個人情報をだまし取られたりする被害が発生します。
クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)
クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)は、ログイン状態のユーザー本人になりすまし、そのユーザーの意図しない処理(商品の購入、退会、パスワードの変更など)をWebアプリケーションに実行させる攻撃です。 攻撃者は罠サイトを用意し、そこを訪れたユーザーが気づかないうちに、標的のWebサイトへ不正なリクエストを送信させます。
ディレクトリトラバーサル
ディレクトリトラバーサルは、ファイル名を指定するプログラムの不備を悪用し、本来アクセスが許可されていないディレクトリ(フォルダ)やファイルに不正にアクセスする攻撃です。 URLに含まれるファイルパスに「../」のような文字列を挿入することで上位のディレクトリへ移動し、設定ファイルやパスワードファイルなど、公開を意図しない機密情報を盗み見られてしまう危険性があります。
リモートコード実行(RCE)
リモートコード実行(Remote Code Execution)は、脆弱性を利用して、攻撃者が遠隔(リモート)から標的のサーバー上で任意のプログラムコード(コマンド)を実行する攻撃です。成功すれば、サーバーを完全に乗っ取られ、データの窃取や改ざん、マルウェアの設置、他のシステムへの攻撃の踏み台にされるなど、極めて深刻な被害につながる可能性があります。
このような巧妙化するWebアプリケーションへの攻撃手法や、その対策についてより深く学びたい方には、専門家が解説するセミナーへの参加も有効です。最新の脅威動向や防御策について体系的に理解を深めることができます。
人を標的とする攻撃
システムの脆弱性だけでなく、人間の心理的な隙やミスを利用する攻撃も数多く存在します。これらは「ソーシャルエンジニアリング」とも呼ばれます。
標的型攻撃
標的型攻撃は、特定の組織や個人を明確な標的として、その標的が持つ機密情報などを窃取するために周到な準備のもとで行われる攻撃です。 標的の業務内容や取引先を事前に詳しく調査し、業務に関係があるかのような巧妙な偽装メール(スピアフィッシングメール)を送りつけ、マルウェアに感染させます。一度侵入すると、長期間潜伏しながら活動を続けることが多く、このような持続的な攻撃は特にAPT(Advanced Persistent Threat:高度持続的脅威)攻撃と呼ばれます。
フィッシング・スミッシング
フィッシングは、実在する金融機関やECサイトなどを装った偽のメールやWebサイトへ誘導し、ID、パスワード、クレジットカード情報などを入力させてだまし取る詐欺の手口です。近年では、SMS(ショートメッセージサービス)を利用した「スミッシング」の被害も急増しています。 宅配便の不在通知や料金未納の通知などを装い、偽サイトへ誘導する手口が典型的です。
組織の繋がりを悪用する攻撃
自社だけでなく、取引先や関連会社など、ビジネス上の繋がりを悪用して標的に侵入する、より巧妙な攻撃手法です。
サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃は、標的とする企業へ直接攻撃するのではなく、セキュリティ対策が比較的脆弱な取引先や子会社、業務委託先などを経由して侵入を試みる攻撃です。 標的企業が強固なセキュリティを築いていても、サプライチェーンを構成するどこか一社でも脆弱性があれば、そこが侵入の足がかりとされてしまいます。ソフトウェアの開発元が攻撃を受け、正規のアップデートファイルにマルウェアが混入させられるといったケースもあります。
ゼロデイ攻撃
ゼロデイ攻撃は、OSやソフトウェアに脆弱性が発見されてから、開発元が修正プログラム(パッチ)を提供するまでの期間(ゼロデイ)を狙って行われる攻撃です。 対策が世に出ていない未知の脆弱性を突くため、ウイルス対策ソフトなど従来の防御策では検知が極めて困難であり、非常に深刻な脅威とされています。
サイバー攻撃が企業に与える影響は?
サイバー攻撃は、単なるシステムトラブルでは済みません。一度被害に遭うと、企業の存続そのものを揺るしかねない甚大な影響を及ぼします。その影響は「金銭的損失」「事業継続」「信用の失墜」という、企業経営の根幹をなす3つの側面に深刻なダメージを与えます。
金銭的損失:復旧費用から賠償金まで
サイバー攻撃がもたらす最も直接的な影響は、金銭的な損失です。攻撃によって発生するコストは多岐にわたり、中小企業であっても数千万円から数億円規模の損害に至る可能性があります。 具体的な損失は、直接的損害と間接的損害(費用損害)に大別できます。
| 損害の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 直接的損害 |
|
| 間接的損害(費用損害) |
|
これらの費用は、インシデントが発覚した直後から発生し始め、事態が収束した後も継続的に企業の財務を圧迫します。特に、個人情報が漏えいした場合の損害賠償額は、被害者の人数に比例して膨れ上がるため、企業の経営基盤を根底から覆すリスクをはらんでいます。
事業継続への影響:業務停止のリスク
サイバー攻撃は、企業の事業活動そのものを停止させる深刻なリスクをもたらします。 ランサムウェアによって基幹システムや生産管理システムが暗号化されれば、受注、生産、出荷といったサプライチェーン全体が麻痺し、長期間の業務停止に追い込まれることがあります。
実際に、国内の自動車部品メーカーがランサムウェア攻撃を受けた際には、親会社である大手自動車メーカーの国内全工場が稼働停止に追い込まれるという事態に発展しました。 また、大手飲料メーカーが攻撃を受けた際には、全国でビールの供給に混乱が生じるなど、その影響は自社にとどまらず社会全体に及びました。
被害からの復旧には、単にデータを元に戻すだけでなく、原因究明、脆弱性の解消、再発防止策の徹底といったプロセスが必要となり、完全復旧までに数週間から数ヶ月を要することも少なくありません。 この間の事業停止は、売上機会の損失だけでなく、顧客や取引先からの信頼を大きく損なうことにも直結します。
信用の失墜:顧客離れとブランドイメージ低下
サイバー攻撃が企業に与える影響の中で、最も回復が困難なのが「信用の失墜」です。情報漏えいやサービス停止といった事態は、顧客や取引先に「セキュリティ管理が甘い企業」というネガティブな印象を与え、ブランドイメージを著しく毀損します。
一度失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。顧客は個人情報の流出を懸念してサービスから離れ、取引先はサプライチェーンリスクを回避するために契約を見直す可能性があります。 近年では、インシデント発生後の企業の対応がSNSなどで拡散し、「炎上」することでさらに評判を落とすケースも増えています。
Kaspersky Labの調査によれば、情報漏えいを経験した企業の半数がブランドイメージの低下に苦しんでおり、それが利益の減少や、最悪の場合には倒産につながることもあると指摘されています。 このように、サイバー攻撃は目に見える金銭的損害以上に、企業が長年かけて築き上げてきた信頼という無形の資産を一瞬にして奪い去る、恐ろしい脅威なのです。
自社のセキュリティ体制を見直し、最新の脅威動向を把握するためにも、セキュリティ専門家が開催するイベントやセミナーに参加することは有効な手段です。最新の攻撃事例や対策技術について情報を収集し、自社の防御力向上に役立てましょう。
実際に起きたサイバー攻撃の被害事例から学ぶ
サイバー攻撃は、もはや他人事ではありません。ここでは国内外で実際に発生し、社会に大きな影響を与えたサイバー攻撃の事例を紹介します。自社が同様の被害に遭わないためにも、これらの事例から教訓を学び取ることが重要です。
国内企業の被害事例
日本国内でも、企業の規模や業種を問わず、サイバー攻撃による被害が後を絶ちません。特に近年は、事業の根幹を揺るがすような深刻な事例が頻発しています。
ランサムウェアによる業務停止事例
ランサムウェア攻撃は、企業の事業継続に深刻なダメージを与える脅威です。国内でも多くの企業が被害に遭い、長期間の業務停止や多額の復旧費用といった甚大な影響を受けています。
| 被害組織 | 発生時期 | 概要 |
|---|---|---|
| 大手自動車メーカーの取引先部品メーカー | 2022年3月 |
取引先である部品メーカーがランサムウェア攻撃を受けシステム障害が発生。これにより部品の供給が停止し、大手自動車メーカーは国内全14工場28ラインの稼働を一時停止する事態に追い込まれました。 この事例は、サプライチェーン上の1社の被害が、業界全体にいかに大きな影響を及ぼすかを明確に示しました。 |
| 大手製粉企業 | 2021年7月 |
グループ会社が管理するネットワーク経由で侵入され、基幹システムやバックアップサーバーまで暗号化される被害が発生。 復旧が困難を極め、決算報告書の提出を約3ヶ月延期するなど、経営にも大きな支障をきたしました。 |
サプライチェーン攻撃による情報漏えい事例
セキュリティ対策が比較的脆弱な取引先や子会社を踏み台にして、最終的な標的である大企業へ侵入するサプライチェーン攻撃の被害も深刻化しています。
| 被害組織 | 発生時期 | 概要 |
|---|---|---|
| 複数の保険会社 | 2023年1月 |
業務委託先のサーバーが不正アクセスを受け、最大で約130万人分にも上る顧客情報が漏えい。漏えいした情報は海外のWebサイトに掲載される事態となりました。この事例は、自社のセキュリティ対策だけでなく、委託先を含めたサプライチェーン全体での管理体制の重要性を浮き彫りにしました。 |
| 大手電機メーカーの海外子会社 | 2023年6月 |
海外のグループ企業がランサムウェアの攻撃を受け、ネットワークに侵入されました。 この攻撃により、顧客情報や従業員情報を含む機密データが暗号化され、国内外のグループ9社にまで影響が拡大しました。 グローバルに展開する企業にとって、セキュリティレベルが比較的低い海外拠点が攻撃の起点となりうることを示す教訓的な事例です。 |
自社のセキュリティ対策を強化することはもちろんですが、現代のビジネス環境ではそれだけでは不十分です。セキュリティに関する最新の動向や対策事例を学ぶためには、専門家が集うイベントやセミナーへの参加が有効です。ぜひ「セキュリティ関連イベント・セミナー情報」をチェックし、対策強化にお役立てください。
海外の重大インシデント事例
海外では、国家の安全保障を脅かすほど大規模なサイバー攻撃も発生しています。これらの事例は、サイバー攻撃がもたらす影響の大きさを物語っています。
SolarWinds社へのサプライチェーン攻撃
2020年に発覚したこの事件は、史上最大規模とも言われる巧妙なサプライチェーン攻撃です。攻撃者は、ITインフラ管理ソフトウェアを開発するSolarWinds社の正規アップデートファイルにバックドアを仕込みました。 これにより、そのソフトウェアを利用していたアメリカの政府機関(国防総省、財務省など)や大手企業を含む、世界中の約18,000の組織が影響を受けたとされています。 長期間にわたり気づかれることなく機密情報が窃取された可能性があり、サイバー攻撃の脅威を世界中に再認識させました。
Colonial Pipeline社へのランサムウェア攻撃
2021年5月、米国最大級の石油パイプラインを運営するColonial Pipeline社がランサムウェア攻撃の被害に遭いました。 この攻撃により、同社はパイプラインの操業を約5日間停止せざるを得なくなり、アメリカ東海岸の燃料供給の約45%がストップ。 ガソリン不足への懸念からパニック買いが起き、ガソリン価格が高騰するなど、社会インフラを標的としたサイバー攻撃が市民生活に直接的な影響を及ぼすことを示す象徴的な事件となりました。 同社は攻撃者に対し、約440万ドル相当の暗号資産を身代金として支払ったと報じられています。
重要インフラが標的となった事例
電力、ガス、水道、交通といった重要インフラは、ひとたびサイバー攻撃を受ければ国民生活や経済活動に甚大な被害を及ぼすため、特に厳重なセキュリティ対策が求められます。しかし、国内外で重要インフラを標的とした攻撃は現実に発生しています。
名古屋港のコンテナターミナルシステム停止
2023年7月、日本最大の国際貿易港である名古屋港で、コンテナターミナルの管理システム「NUTS」がランサムウェア「LockBit」に感染しました。 この影響で、コンテナの搬出入作業が全面的に停止し、約2日半にわたり港湾機能が麻痺。 日本の物流の要である港湾がサイバー攻撃によって停止した初の事例とされ、経済活動への影響の大きさが懸念されました。 調査の結果、リモート接続に用いるVPN機器の脆弱性が侵入経路であった可能性が指摘されています。
ウクライナの電力網への攻撃
2015年12月、ウクライナの電力会社がサイバー攻撃を受け、約22万5千世帯が最大6時間にわたり停電するという事態が発生しました。 これは、サイバー攻撃によって大規模な停電が引き起こされた世界初の事例とされています。 攻撃者は、標的型メールでマルウェア「BlackEnergy」に感染させた後、遠隔操作で送電システムのブレーカーを不正に遮断しました。 さらに、復旧作業を妨害するためにコールセンターへDDoS攻撃を行うなど、極めて計画的かつ複合的な攻撃でした。 この事件は、重要インフラ、特に電力網が国家間の対立において標的となりうることを示唆しています。
企業が講じるべき具体的なサイバー攻撃対策
サイバー攻撃の脅威は、もはや対岸の火事ではありません。企業の規模や業種を問わず、すべての組織が攻撃対象となりうる現代において、被害を未然に防ぎ、万が一の事態にも迅速に対応できる体制を構築することは、事業継続における最重要課題の一つです。本章では、企業が具体的に講じるべきサイバー攻撃対策を「技術的対策」「組織的対策」「インシデント対応」の3つの側面に分けて、網羅的に解説します。
自社を守るための技術的対策7選
技術的対策は、サイバー攻撃の侵入を防ぎ、被害を最小限に抑えるための物理的・システム的な防御策です。多層的な防御を意識し、複数の対策を組み合わせることが極めて重要となります。
セキュリティサービスの導入
巧妙化するサイバー攻撃から自社システムを守るためには、専門的なセキュリティサービスの導入が不可欠です。それぞれのサービスが持つ役割を理解し、自社の環境に合わせて多層的に防御を固めることが重要です。
| サービス種別 | 主な役割と防御対象 |
|---|---|
| ファイアウォール | ネットワークの出入り口で通信を監視し、許可されていない不正な通信を遮断します。社内ネットワークを外部の脅威から守る基本的な対策です。 |
| WAF(Web Application Firewall) | Webアプリケーションの脆弱性を狙った攻撃(SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティングなど)を検知・防御します。WebサイトやWebサービスを公開している場合に必須の対策です。 |
| IDS/IPS(不正侵入検知/防御システム) | ネットワークやサーバーへの不正なアクセスやその兆候を検知し、管理者に通知(IDS)または自動的にブロック(IPS)します。ファイアウォールをすり抜けた攻撃を検知する役割を担います。 |
| EDR(Endpoint Detection and Response) | PCやサーバーなどのエンドポイント(端末)の操作を監視し、マルウェア感染後の不審な挙動を検知・分析して対応を支援します。アンチウイルスソフトだけでは防ぎきれない未知の脅威への対策として近年重要性が高まっています。 |
| SIEM(Security Information and Event Management) | 様々なセキュリティ機器やサーバーのログを一元的に収集・分析し、脅威の相関分析やインシデントの早期発見を可能にします。組織全体のセキュリティ状況を可視化し、迅速な対応を支援します。 |
これらのサービスを適切に組み合わせることで、堅牢なセキュリティ体制を構築できます。自社のセキュリティ課題やリスクを洗い出し、必要なサービスを選定することが第一歩です。どのようなソリューションがあるか知りたい方は、各種セキュリティ製品をまとめた「三和コムテック Security Solution Book」もご活用ください。
社内ネットワークのアクセス制御
万が一、ネットワーク内部への侵入を許した場合でも、被害を最小限に食い止めるためにアクセス制御の徹底が重要です。「ゼロトラスト」の考え方に基づき、「すべてのアクセスは信頼できない」という前提で対策を講じる必要があります。
具体的には、従業員やサーバーに対し、業務上必要最小限の権限のみを与える「最小権限の原則」を適用します。また、ネットワークを機能や部署ごとに細かく分割(セグメンテーション)し、セグメント間の通信を厳しく制限することで、マルウェアがネットワーク全体に広がる(ラテラルムーブメント)のを防ぎます。
セキュリティアップデート
OSやソフトウェア、ネットワーク機器に存在する脆弱性は、サイバー攻撃の主要な侵入口となります。開発元から提供されるセキュリティパッチを迅速に適用し、システムを常に最新の状態に保つことは、基本的ながら非常に効果的な対策です。脆弱性管理ツールなどを活用し、自社で利用しているIT資産の脆弱性情報を常に把握し、計画的にアップデートを適用する体制を構築することが求められます。
多要素認証(MFA)の導入
IDとパスワードだけの認証では、パスワードリスト攻撃やブルートフォース攻撃によって容易に突破される危険性があります。多要素認証(MFA)は、知識情報(パスワードなど)、所持情報(スマートフォンアプリの認証コードなど)、生体情報(指紋、顔認証など)のうち、2つ以上を組み合わせて認証を行う仕組みです。VPNやクラウドサービス、特権IDなど、重要な情報資産へアクセスする際にはMFAを必須とすることで、不正ログインのリスクを大幅に低減できます。
人的ミスを防ぐ組織的対策4選
どれだけ高度な技術的対策を導入しても、それを利用する「人」のセキュリティ意識が低ければ、その穴を突かれてしまいます。従業員一人ひとりのセキュリティリテラシー向上と、組織としてのルール作りが不可欠です。
従業員へのセキュリティ教育
標的型攻撃メールやフィッシング詐欺など、人を騙す手口の攻撃は後を絶ちません。これらの攻撃を防ぐには、従業員一人ひとりが脅威を正しく認識し、適切に対処できる能力を身につける必要があります。不審なメールの見分け方、安全なパスワードの管理方法、情報資産の取り扱いルールなどについて、定期的な研修やeラーニング、標的型攻撃メール訓練を実施し、組織全体のセキュリティ意識を継続的に向上させることが重要です。
最新のセキュリティ動向や対策について学ぶ場として、各種「セキュリティ関連イベント・セミナー情報」もご活用いただけます。
バックアップ体制の整備
ランサムウェア攻撃など、データを人質に取る攻撃への最も有効な対策の一つが、データのバックアップです。しかし、単にバックアップを取るだけでは不十分です。重要なのは、攻撃の影響を受けない場所にデータを保管し、かつ迅速に復旧できる体制を整えておくことです。バックアップデータは、ネットワークから隔離されたオフライン環境や、データの書き換えができないイミュータブルストレージに保管することが推奨されます。また、定期的に復旧テストを行い、いざという時に確実にデータを元に戻せることを確認しておく必要があります。
インシデント対応計画の策定
サイバー攻撃の被害を完全にゼロにすることは困難です。そのため、インシデント(セキュリティ事故)が発生することを前提に、事前に行動計画を策定しておくことが極めて重要です。インシデント対応計画には、インシデント発生時の報告体制(誰が、誰に、何を報告するのか)、対応チーム(CSIRTなど)の役割分担、外部専門家や関係機関(警察、IPA、JPCERT/CCなど)への連絡手順などを具体的に定めておきます。計画を策定し、定期的に訓練を行うことで、有事の際にも慌てず、冷静かつ迅速な対応が可能になります。
もし攻撃されたら?インシデント対応のフロー
実際にサイバー攻撃の被害が疑われる場合、パニックに陥らず、定められた手順に従って冷静に対応することが被害の最小化に繋がります。一般的なインシデント対応は、以下のフェーズで進められます。
- 検知と分析: システムの異常やアラートを検知し、それがインシデントであるかを判断します。ログを分析し、攻撃の手法や影響範囲の特定(トリアージ)を行います。
- 初動対応(封じ込め): 被害の拡大を防ぐため、感染した端末をネットワークから隔離したり、不正アクセスされたアカウントを停止したりします。迅速な封じ込めが、被害を最小限に抑える鍵となります。
- 原因の調査と根絶: 攻撃の原因となった脆弱性やマルウェアを特定し、システムから完全に排除します。必要に応じて、専門のフォレンジック調査会社と連携します。
- 復旧: 脅威が排除されたことを確認した後、クリーンなバックアップからシステムやデータを復旧させ、サービスを再開します。復旧後も、再発がないか監視を継続します。
- 事後対応と報告: 監督官庁や警察、顧客、取引先など、関係各所への報告を行います。今回のインシデントから得られた教訓を基に再発防止策を策定し、セキュリティポリシーや運用体制を見直します。
インシデント対応は専門的な知識を要するため、自社だけで対応が困難な場合は、速やかに外部の専門機関に支援を要請することが重要です。最新の脅威情報や対策を常に把握しておくために、「三和コムテックが提供する最新ブログ無料購読」をご活用ください。また、記事中の専門用語については「分かりやすいセキュリティ用語集」で詳しく解説しています。
IPA「情報セキュリティ10大脅威 2025」から読み解く最新動向
組織の情報セキュリティ対策を進める上で重要な指針となるのが、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が毎年発表する「情報セキュリティ10大脅威」です。 このレポートは、前年に発生した社会的に影響の大きいセキュリティ事案を基に、専門家たちの審議と投票によって、その年に特に警戒すべき脅威をランキング形式で示しています。 2025年版も、現代のサイバー攻撃のトレンドを色濃く反映した内容となっており、企業が優先的に取り組むべき課題を明確にしています。
情報セキュリティ10大脅威 2025【組織編】ランキング
2025年1月に発表された「情報セキュリティ10大脅威 2025」の組織向けランキングは以下の通りです。 「ランサムウェアによる被害」が10年連続で1位となり、依然として企業にとって最大の脅威であることが示されました。 また、2位の「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」も7年連続でのランクインとなり、自社だけでなく取引先を含めたセキュリティ対策の重要性が浮き彫りになっています。 さらに、2025年版では新たに「地政学的リスクに起因するサイバー攻撃」が登場し、国際情勢がサイバー空間にも大きな影響を与えていることがわかります。
| 順位 | 脅威 | 概要 |
|---|---|---|
| 1位 | ランサムウェアによる被害 | データを暗号化し、復旧と引き換えに金銭を要求する攻撃。近年はデータの暴露も組み合わせた二重脅迫が主流。 |
| 2位 | サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 | セキュリティ対策が手薄な取引先や子会社を踏み台にし、標的の組織へ侵入する攻撃。 |
| 3位 | 内部不正による情報漏えい等の被害 | 従業員や元従業員など、組織関係者が意図的に機密情報を持ち出し、悪用する行為。 |
| 4位 | 標的型攻撃による機密情報の窃取 | 特定の組織を狙い、業務に関連するメールを装うなど巧妙な手口でマルウェアに感染させ、情報を盗み出す攻撃。 |
| 5位 | 修正プログラムの公開前を狙う攻撃(ゼロデイ攻撃) | OSやソフトウェアの脆弱性が発見され、修正パッチが提供される前にその弱点を悪用する攻撃。 |
| 6位 | 不注意による情報漏えい等の被害 | メールの誤送信、PCや記憶媒体の紛失、設定ミスなど、人的なミスが原因で情報が漏えいするケース。 |
| 7位 | ビジネスメール詐欺(BEC)による金銭被害 | 経営者や取引先になりすまして偽のメールを送り、送金指示などを通じて金銭をだまし取る詐欺。 |
| 8位 | 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 | ソフトウェアなどの脆弱性情報が公開された後、修正パッチを適用していないシステムを狙った攻撃。 |
| 9位 | テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 | VPN機器の脆弱性や、私物端末の利用など、オフィス外での業務環境のセキュリティの隙を狙う攻撃。 |
| 10位 | 犯罪のビジネス化(アンダーグラウンドサービス) | 攻撃用のツールや盗まれた情報がアンダーグラウンド市場で売買され、誰でも容易にサイバー攻撃を実行できる状況。 |
より詳細な情報については、IPAが公開している「情報セキュリティ10大脅威 2025」の解説書も併せてご参照ください。
2025年に特に警戒すべき脅威の動向
ランキング上位の脅威は、いずれも手口が巧妙化・高度化しており、企業は継続的な対策の見直しを迫られています。特に以下の脅威については、最新の動向を理解し、対策を強化することが急務です。
ランサムウェア攻撃の深刻化と巧妙化
ランサムウェア攻撃は、単なるデータ暗号化にとどまらず、窃取した情報を公開すると脅す「二重脅迫」が一般化しています。 近年では、DDoS攻撃を仕掛けて業務を妨害する「三重脅迫」や、被害企業の顧客や取引先にまで連絡を取って圧力をかける「四重脅迫」といった、より悪質な手口も確認されています。2023年7月に発生した名古屋港のコンテナターミナルでのシステム障害のように、重要インフラが標的となり、社会活動に深刻な影響を及ぼす事例も発生しており、事業継続計画(BCP)の観点からも対策が不可欠です。
サプライチェーン攻撃の連鎖リスク
セキュリティ対策が強固な大企業を直接狙うのではなく、取引関係にあるセキュリティの脆弱な中小企業が攻撃の起点とされるケースが増加しています。 ソフトウェア開発の委託先や、クラウドサービス提供事業者などが侵入経路として悪用されることも少なくありません。 自社のセキュリティを強化するだけでなく、委託先の管理体制の確認や、サプライチェーン全体でのセキュリティレベル向上に向けた取り組みが求められます。
生成AIの悪用と新たな脅威
2025年以降、生成AIを悪用したサイバー攻撃が本格化すると予測されています。 例えば、AIを用いて極めて自然で巧妙なフィッシングメールの文面を大量に作成したり、マルウェアのコードを自動生成したりすることが可能になります。 また、ディープフェイク技術を用いて経営者の声や映像を偽造し、従業員を騙して不正送金させるような新たなビジネスメール詐欺(BEC)の発生も懸念されています。従来の対策だけでは見抜くことが困難な、より高度な攻撃への備えが必要です。
このように日々進化するサイバー攻撃の脅威から自社を守るためには、常に最新の情報を収集し、対策をアップデートし続けることが不可欠です。三和コムテックでは、セキュリティに関する最新の脅威情報や対策方法を解説するブログを定期的に更新しており、無料で購読いただけます。また、サイバー攻撃を理解する上で必要となる専門用語については、「分かりやすいセキュリティ用語集」をご用意しています。ぜひ、貴社のセキュリティ対策強化にお役立てください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 中小企業でもサイバー攻撃の対策は必要ですか?
はい、絶対に必要です。近年、セキュリティ対策が強固な大企業を直接狙うのではなく、取引先である中小企業を踏み台にする「サプライチェーン攻撃」が急増しています。自社が被害を受けるだけでなく、取引先へ被害を拡大させる加害者になるリスクもあるため、企業規模に関わらず対策は必須と言えます。
Q2. サイバー攻撃を受けたら、まず何をすべきですか?
まずは被害の拡大を防ぐことが最優先です。具体的には、感染が疑われる端末を速やかにネットワークから物理的に切り離し(LANケーブルを抜く、Wi-Fiを切るなど)、すぐに情報システム部門やセキュリティ担当者へ報告してください。事前にインシデント対応のフローを決め、全従業員に周知しておくことが迅速な初動対応に繋がります。
Q3. 最も警戒すべきサイバー攻撃は何ですか?
IPAが発表する「情報セキュリティ10大脅威」では、組織部門において「ランサムウェアによる被害」が長年1位となっています。事業停止に追い込まれるなど経営に深刻なダメージを与えるため、最も警戒すべき攻撃の一つです。また、特定の組織を狙い巧妙な手口で侵入する「標的型攻撃」や、前述の「サプライチェーン攻撃」も依然として高い脅威です。
Q4. 無料のセキュリティソフトだけで対策は十分ですか?
残念ながら、無料のセキュリティソフトだけでは不十分です。近年のサイバー攻撃は手口が非常に巧妙化しており、ウイルス対策ソフトだけでは防ぎきれません。ファイアウォール、不正侵入検知システム(IDS/IPS)、WAF(Web Application Firewall)など、複数の対策を組み合わせた「多層防御」の考え方が不可欠です。
Q5. 従業員のセキュリティ意識を高めるには、どうすれば良いですか?
定期的なセキュリティ教育と、実践的な訓練が有効です。フィッシングメールの見分け方やパスワード管理の重要性といった知識をインプットするだけでなく、実際に標的型攻撃メールを模した訓練メールを送付し、開封してしまった従業員に再度教育を行うなど、継続的な取り組みが従業員の意識向上に繋がります。
まとめ
本記事では、サイバー攻撃の基礎知識から具体的な手口、企業が受ける影響、そして講じるべき対策までを網羅的に解説しました。サイバー攻撃の手法は日々進化・巧妙化しており、もはやどの企業にとっても対岸の火事ではありません。攻撃を受けてからでは、金銭的損失、事業停止、そして社会的信用の失墜といった計り知れないダメージを被る可能性があります。
重要なのは、最新の脅威動向を常に把握し、「技術的対策」と「組織的対策」の両輪で、自社のセキュリティ体制を継続的に見直し、強化していくことです。ウイルス対策ソフトの導入といった基本的な対策はもちろん、ネットワークのアクセス制御、従業員への教育、インシデント発生時を想定した対応計画の策定まで、多角的な視点で備えることが不可欠です。
もし、自社のセキュリティ対策に少しでも不安を感じたり、何から手をつければ良いか分からなかったりする場合には、専門家の知見を活用することをおすすめします。三和コムテックでは、お客様の課題に合わせた最適なセキュリティソリューションをご提案しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
より詳しい情報収集には、以下の資料やコンテンツもぜひご活用ください。
- 網羅的なセキュリティソリューションをまとめた「三和コムテック Security Solution Book」
- 最新の脅威や対策について専門家が解説する「セキュリティ関連イベント・セミナー情報」
- セキュリティの最新情報を見逃さないための「三和コムテックが提供する最新ブログ無料購読」
- 複雑な専門用語をわかりやすく解説した「分かりやすいセキュリティ用語集」
セキュリティソリューションプロダクトマネージャー OEMメーカーの海外営業として10年間勤務の後、2001年三和コムテックに入社。
新規事業(WEBセキュリティ ビジネス)のきっかけとなる、自動脆弱性診断サービスを立ち上げ(2004年)から一環して、営業・企画面にて参画。 2009年に他の3社と中心になり、たち上げたJCDSC(日本カードセキュリティ協議会 / 会員企業422社)にて運営委員(現在,運営委員長)として活動。PCIDSSや非保持に関するソリューションやベンダー、また関連の審査やコンサル、などの情報に明るく、要件に応じて、弊社コンサルティングサービスにも参加。2021年4月より、業界誌(月刊消費者信用)にてコラム「セキュリティ考現学」を寄稿中。
- トピックス:
- セキュリティ
- 関連トピックス:
- サイバー攻撃対策 基礎知識