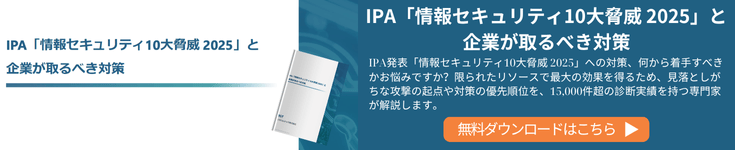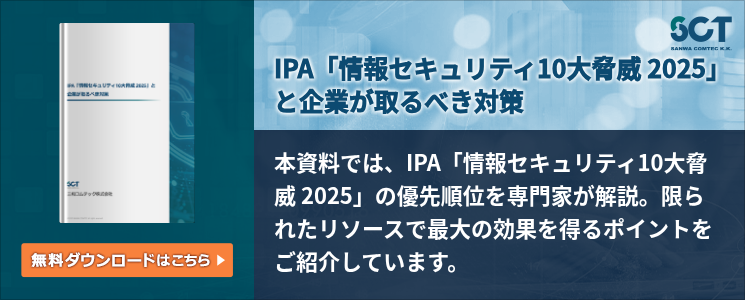「地政学的リスクは本当に自社にも関係があるのだろうか」と感じている方が多いかもしれません。実際には、国際的な緊張や紛争は、輸出入の停滞やサプライチェーンの混乱、さらにはサイバー攻撃を通じて、企業経営に大きな影響を与えます。本記事では、地政学的リスクの種類や日本企業への影響、そして企業が今取るべき具体的な対応策について、分かりやすく解説します。
地政学的リスクとは何か

世界情勢が不安定になる中で、企業活動における「地政学的リスク」への注目が高まっています。日本企業にとっても、グローバルな経済活動を進める中で、これらのリスクは無視できない要素となっており、経営戦略の中で地政学的な視点を持つことの重要性が今後さらに加速することでしょう。
まずは、地政学的リスクの基本的な知識から解説します。
地政学的リスクの定義
地政学的リスクとは、国や地域の政治的、経済的、軍事的な対立や摩擦に起因して発生する不確実性(リスク)を指します。
例えば、特定地域での戦争や紛争、政権交代、経済制裁、外交関係の悪化などが原因で、輸出入の停止、サプライチェーンの混乱、金融市場の動揺などが引き起こされるケースが典型例です。
これらのリスクは企業活動に直結し、事業継続性や収益性に大きな影響を及ぼすため、近年では多くの企業が地政学的リスクを重要な経営課題として捉えています。
地政学的リスクの種類
地政学的リスクは多岐にわたりますが、ここでは代表的なものを紹介します。
- 国家間の政治的対立により外交関係が悪化し、緊張が高まる
- 軍事衝突や、テロなどによる武力行使によって物流の遮断や物的被害が発生する
- 経済制裁や、貿易規制による関税引き上げにより、企業活動に障害が発生する
- 国家レベルでのハッキング活動などのサイバー攻撃を受ける
これらのリスクは単独で現れるだけでなく、複合的に影響し合いながら企業の活動を脅かす点が、対応をより困難にしています。
企業における地政学的リスクの基本的な知識や対策については、こちらの記事も参考にしてください。
日本における地政学的リスクとは何か

日本は島国でありながら、周囲には中国、北朝鮮、ロシアといった地政学的に不安定な国々を抱え、またエネルギーや食糧を海外に依存しているという特性を持ちます。このような特性から、さまざまな地政学的リスクの影響を受けやすい立場にいるのが日本です。
ここでは、日本における地政学的リスクについて5つの側面から解説します。
中国との関係|台湾情勢や南シナ海問題
中国と台湾の関係が緊迫する中、双方と貿易を行っている日本企業はその影響を避けることはできません。
実は、日本の自動車や電機産業は台湾との貿易に大きく依存しています。
仮に台湾に有事が発生すれば、台湾海峡の封鎖や航路の制限により、半導体など重要な電子部品の輸送が停止する恐れがあります。その場合、物流の停滞が連鎖的に製造ラインの停止や納期遅延を引き起こす可能性もあるでしょう。
北朝鮮との関係|ミサイル問題
日本にとって最も近い国の1つである北朝鮮は、大きな地政学的リスクとして注視されています。
北朝鮮は不定期に弾道ミサイルを発射しており、その多くが日本の排他的経済水域(EEZ)付近に落下しています。2024年だけでも、少なくとも10発以上のミサイルが発射されたとされ、緊張感が高まっています。
2025年時点では、ミサイルが日本の領海や領土内に落下した事実は確認されていません。しかし仮に国内に落下すれば、一般市民に被害が及ぶ可能性も否定できません。このような状態が継続すると、日本の安全保障リスクが一層高まるだけでなく、航空路や海上航路といった国際交通の安全性にも深刻な影響を与える恐れがあります。
ロシアとの関係|北方領土問題
日本とロシアの間には、北方領土をめぐる長年の領土問題が存在しています。近年では、ロシアによるウクライナ侵攻を契機に、両国関係は一層悪化しています。
2024年11月、ロシアは日本を含む12カ国を「非友好国」に指定し、国際的な注目を集めました。日本に対して明確な敵対行動を取っているわけではないものの、関係がさらに悪化した場合には、経済面への影響も懸念されます。
例えば、日本が輸入する天然ガスの約1割はロシアからのものであり、仮に供給が途絶えれば、国内エネルギー供給に大きな影響を及ぼす可能性があります。供給不足に伴う価格高騰など、経済的混乱が生じるリスクも無視できません。
食糧安全保障の問題|食糧自給率の低さ
農林水産省によると、日本の食料自給率はカロリーベースで38%と、先進国の中でも極めて低い水準にとどまっています。
特に、畜産業に必要な飼料の約75%以上を海外からの輸入に依存している点は深刻です。そのため、国際情勢の変化によって価格が高騰した場合、供給不安が生じ、畜産物の価格高騰に直結するリスクがあるのです。
このように、日本の食糧安全保障は国際情勢に大きく左右されます。
さらに、国産野菜であっても、異常気象の影響により価格が大きく変動することがあります。実際に、収穫不足が原因で野菜の価格が高騰し、ニュースで話題になるケースも少なくありません。
もし収穫不足による価格高騰と、国際的な穀物争奪戦が重なった場合、食料価格の上昇は企業活動だけでなく、国民生活全体にも深刻な影響を与える可能性があります。
サプライチェーンの問題|途絶や混乱の危機
サプライチェーンとは、商品の企画・開発から、最終消費者に届くまでの「供給の一連の流れ」を指します。
製品の生産はもちろんのこと、原材料の輸入や製品の輸出など、サプライチェーンの中で発生しうるリスクは多く存在します。地政学的リスクで考えた場合、最も影響を受けやすいのが「物流」です。具体的には製品の原材料の輸入や完成した製品の輸出が考えられます。
例えば、2020年に起きた新型コロナウィルスの蔓延により、輸入の際の検疫が強化された結果、関税通過に時間がかかるようになり、結果として流通量が減る、といった事象が発生しました。
これは、紛争によるルート制限や経済制裁による輸入規制が発生した場合、同様のことが起こりうる、ということです。
サプライチェーンの途絶や混乱は、物流コストの上昇、納期遅延、生産の停滞を引き起こし、企業活動へ悪影響を与えることになります。
日本企業が直面する地政学的リスクの現実

グローバル化が進む現代において、日本企業の多くは海外市場に積極的に進出しています。その一方で、進出先の国や地域で発生する地政学的リスクが、企業活動に深刻な影響を及ぼすケースが増えています。
ここでは、日本企業における地政学的リスクについて解説します。
輸出入規制と関税措置の強化
米中の経済摩擦をはじめとした国際的な緊張により、各国は半導体や希少資源といった戦略物資の輸出入規制を強化しています。
例えば、日本は先端半導体製造装置の一部を輸出管理対象に指定しましたが、これに対して中国は重要資源であるガリウムやグラファイトといったレアメタルの輸出制限を実施し、半導体を利用する各業界などへの打撃が拡大しました。
特に影響が大きかったのが自動車業界です。自動車の生産が進まず、納車まで数年待ち、という事象が発生しました。
国家間の衝突
中東や東欧などの地域で続く国家間の衝突も、企業活動への大きなリスクとなっています。
例えば、ロシアによるウクライナ侵攻では、物流や資源価格に大きな混乱が生じました。日本企業も、ロシアとの共同開発プロジェクトの停止や、液化天然ガス輸入の不確実性に直面しました。
こうした武力衝突は直接的な被害をもたらすだけでなく、グローバル市場の信頼性を揺るがし、投資環境やサプライチェーンの再構築に多大なコストを生じさせます。
テロ攻撃や市民による抗議行動
政情不安定な国では、抗議行動やテロ攻撃が日常的に発生しており、日本企業の現地法人や出張者の安全が脅かされています。
例えば、南アジアや中南米では、政府への抗議デモが大規模化することで、物流網の遮断、工場の一時閉鎖、夜間外出の制限といった事態に直面することもあります。
また、テロによってインフラが破壊されたり、供給元の企業が直接被害を受けたりすれば、間接的な操業停止や収益悪化を招くこともあるでしょう。現地に支社や店舗を持つ日本企業は、これらの対応に追われています。
具体的には、安全管理の強化、保険の見直し、危機発生時の代替オペレーションの構築などが重要課題となっています。
地政学的リスクによる企業活動への影響
地政学的リスクは、企業のサプライチェーンや財務、さらにはブランド価値にまで影響を及ぼします。
例えば、以下のような影響が具体的に報告されています。
- 納期遅延・在庫積み増しによるキャッシュフロー悪化
- 送金規制や通貨制限による現地子会社の資金調達困難
- 事業停止に伴う保険未対応リスクや違約金の発生
- 環境・人権リスクの可視化が遅れ、ESG格付けの低下に直結
このように、地政学的リスクは単なる対岸の火事ではありません。日常的な経営リスクとして企業活動に深く関与しているのが実情です。
地政学的リスクに起因するサイバー攻撃の実態

近年、地政学的リスクが「サイバー空間」にも波及し、かつ深刻化しています。IPA(情報処理推進機構)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2025」では、「地政学的リスクに起因するサイバー攻撃」が初めて7位にランクインしました。
サイバー攻撃は国家間の衝突が武力に至る前の「見えない戦争」として、企業・自治体・インフラへの影響が拡大しています。
国家主導のサイバー攻撃とその目的
国家主導のサイバー攻撃は、単なるシステム妨害ではなく、軍事・外交・経済を含めた「ハイブリッド戦争」の一環と位置付けられています。主な目的としては以下が挙げられます。
- 軍事・外交情報の窃取(例:機密文書、通信内容など)
- 重要インフラへの侵入・停止(例:電力、水道、交通機関など)
- 経済混乱の引き起こし(例:金融機関・製造業への攻撃)
- 社会不安の扇動(例:偽情報の流布、世論操作)
こうした攻撃は、相手国の戦略的意思決定を妨害し、その国の混乱を狙うものです。特に政府や自治体だけでなく、民間企業も標的にされることが増えています。
主要な攻撃手法とその脅威
地政学的リスクに関連するサイバー攻撃では、高度化・巧妙化が進んでいます。中でも警戒すべき手法を紹介します。
- 未発見の脆弱性を突いて攻撃する「ゼロデイ攻撃」は、修正パッチが存在せず、被害が拡大しやすいという特徴を持つ
- 取引先や関連企業を介して侵入する「サプライチェーン攻撃」は、取引先などを経由してマルウェアの感染が広がる
- 正規のツールやOSコマンドを悪用する「LotL(Living off the Land)」は、マルウェア対策を回避して攻撃を行う
特にLotLはログの記録が残りにくいため検知が困難で、長期間の潜伏と情報窃取が可能です。LotLについては、事例を含めこのあと解説します。
日本を狙った攻撃の事例
日本国内でも、地政学的背景に基づいたサイバー攻撃がすでに多数確認されています。
ここでは、代表的な例を3つ紹介します。
日本の自治体サービスへのサイバー攻撃
2024〜2025年にかけて、複数の自治体でDDoS(分散型サービス妨害)攻撃やランサムウェア被害が報告されています。
2024年10月、ロシアを支持するハッカー集団は日米軍事演習に対する抗議のため、日本の自治体や交通機関等のWebサイトに対してサイバー攻撃を行ったことをSNSに投稿しました。
実際に同じタイミングで以下のようなサイバー攻撃の被害が発生しています。
- 山梨県のWebサイトへ海外からアクセスが集中し、4時間ほど閲覧しにくい状態が続いた
- 名古屋市、福岡空港、北海道のフェリー会社等のWebサイトが、一時的に閲覧しにくい状態になった
このように、自治体のサービスが攻撃を受け、国内に住む日本人に影響が発生しているのが事実です。
LotL戦術による標的型攻撃
比較的新しい攻撃手法として注目されているのが「LotL戦術」です。この手法は2024年6月に確認され、各方面で注意喚起が行われました。
LotLとは「Living off the Land」の略で、直訳すると「現地調達で生き延びる」という意味を持ちます。セキュリティツールやOSに組み込まれている正規の機能やコマンドを悪用することで、不正な挙動を隠しながら攻撃を行うのが特徴です。マルウェアなどの外部プログラムを使用せず、侵入先のシステムそのものを利用して攻撃するため、この名称が付けられました。
LotL戦術では、企業や組織のネットワークとインターネットの境界にあるセキュリティ機器の脆弱性が狙われるケースが多く見られます。特定のマルウェアを使用しないため、従来のマルウェア対策ソフトでは検知が困難です。
これまでの防御手段が通用しない可能性があることを認識し、振る舞い検知やゼロトラストアーキテクチャの導入など、新たな対策が求められます。
日本の個人や組織に対する標的型攻撃
標的型攻撃は、従来よりセキュリティリスクとして上位にランクインをし続ける存在ですが、近年では地政学的な観点でも被害が拡大しています。
2025年1月に、警察庁および内閣サイバーセキュリティセンターは個人や組織に対するサイバー攻撃が発生し続けていることを発表し、注意喚起を行っていました。
個人や組織に対する標的型攻撃は2024年6月頃から多く発生しており、この攻撃は「MirrorFace」と呼ばれるサイバー攻撃グループによるものであると発表されています。攻撃の対象としては、日本の学術機関、シンクタンク、政治家、マスコミに関係する人物が挙げられており、情報窃取が主な目的です。
サイバー攻撃が引き起こす社会的・経済的影響
サイバー攻撃による被害は、単なる情報漏洩やシステム停止にとどまりません。
「情報セキュリティ10大脅威 2025」において、「地政学的リスクに起因するサイバー攻撃」が初めて7位にランクインしたということは、それだけ攻撃を受けている企業が急増した、ということです。
特に、日本の中でも「攻撃に成功した場合に社会的インパクトが大きい企業」が狙われやすいとされています。具体的には、企業規模が大きい企業や、重要なインフラを担う企業が対象となり得ます。
しかし、「中小企業だから安心」というわけではありません。無差別に攻撃をしかけ、そこから別の企業へ攻撃を仕掛ける「サプライチェーン攻撃」の被害を受ける場合もあります。そのため、地政学的リスクという観点で考慮すると、「日本の企業であれば企業規模・業種に関係なくサイバー攻撃を受けるリスクがある」と考えても差し支えないでしょう。
日本企業ができる地政学的リスク対応策

地政学的リスクは「なにかが起こってから対応する」のでは手遅れになるケースが多く、平時から備えておく必要があります。
特にグローバルに展開をしている日本企業ほど、リスクの種類も多様化・複雑化しており、情報収集・評価・技術・可視化の4つの観点から、計画的に体制を整備していくことが必要です。
地政学的リスク情報の収集
地政学的リスク対策の第一歩となるのが、正確かつ最新の地政学的リスク情報を継続的に収集する体制を構築することです。
日本国内だけでなく、世界的な情勢を把握することが求められるでしょう。地域・国家間での政治的な問題や、貿易問題など、さまざまな情報を収集します。
2020年代に入り多くの地政学的リスク情報が確認されています。2022年に開始したロシアのウクライナ侵攻や、2025年にはアメリカが中国に対して関税の大幅引き上げなどが具体例です。
このような情報は、外務省の海外安全情報やJETRO(日本貿易振興機構)などでも確認できますので、定期的に確認するとよいでしょう。
リスク評価の実施
収集した情報をもとに、企業活動にどのような影響が及ぶのかを定量的に評価します。
具体的には、「発生する可能性(確率)と発生した場合の被害額」をセットで考え、評価します。
特に地政学的リスクを考える場合、世界的な情勢によって発生する可能性が一気に高まったり、被害額が状況によって大きく変動したりする可能性があります。そのため、状況を正確に把握し、正しく評価する必要があると考えてください。
評価の手順としては、以下のことを実施します。
- 重要拠点、主要サプライヤー、輸送ルートを地図上にプロットし、影響範囲を可視化
- それぞれのリスクに対するシナリオ(例:航路封鎖や関税強化など)を想定し、財務的損失、納期への影響、ブランド毀損などを数値化
- 優先度に応じたBCP(事業継続計画)とサプライチェーンの見直しを実施
技術面での対応策
技術的な対策も重要です。特にサイバー攻撃や物流混乱に備えるためには、ITと業務システムの冗長性を確保するとよいでしょう。
- ゼロトラストセキュリティの導入とEDR(エンドポイント検出と対応)による早期侵入検知
- クラウドDR(災害復旧)システムで、データや基幹業務を地理的に分散バックアップ
- AIを活用したサプライチェーン需要予測や代替調達ルートのシミュレーション
- 輸送・製造設備へのIoTセンサーによるリアルタイム監視体制の導入
これらの対策は、地政学的リスクに限らず、一般的なセキュリティ対策として有効なものも存在します。地政学的リスク以外のリスクも考慮し、これらの対策を講じることでより効果的な対応が期待できるでしょう。
リスクを可視化する
地政学的リスクを社内の誰もが理解できるように可視化することで、経営判断のスピードと質が向上します。
具体的には、以下が考えられます。
- GIS(地理情報システム)を活用し、拠点・物流網・リスクエリアを地図で一覧化する
- 各拠点・サプライヤーごとのKRI(Key Risk Indicator:主要リスク指標)を設定し、閾値を超えた際に通知する
- 月次や週次で経営会議へレポーティングし、リスク感度を全社で共有する
特に、グローバルに展開する企業の場合は、現地の工場や支店等を取り巻く情勢を見極め、適切な対処をする必要があります。地政学的リスクは地域における活動に直結するリスクが大半を占めるため、経営層だけではなく全ての社員が影響を受ける可能性が高いです。
正しい対策をするためにも、現場・調達・IT・法務など全社横断で可視化する、という意識醸成が重要です。
まとめ

地政学的リスクは、もはや一部の大企業や特定の地域に限った話ではありません。エネルギー・食料・技術の多くを海外に依存している日本にとって、国際情勢の変化は直接的な経営リスクへとつながります。
地政学的リスクはコントロール不可能な外部要因ではありますが、備えることによって被害を最小化し、逆に競争優位にも変えられるリスクです。先を見据えた行動こそが、これからの企業の持続可能な成長と安定の鍵になるでしょう。
三和コムテックでは、情報セキュリティの脅威に対して企業が取るべき対策を公開しています。地政学的リスクを含め、日本における情報セキュリティの脅威とその対策について分かりやすく解説していますので、ぜひご確認ください。
セキュリティソリューションプロダクトマネージャー OEMメーカーの海外営業として10年間勤務の後、2001年三和コムテックに入社。
新規事業(WEBセキュリティ ビジネス)のきっかけとなる、自動脆弱性診断サービスを立ち上げ(2004年)から一環して、営業・企画面にて参画。 2009年に他の3社と中心になり、たち上げたJCDSC(日本カードセキュリティ協議会 / 会員企業422社)にて運営委員(現在,運営委員長)として活動。PCIDSSや非保持に関するソリューションやベンダー、また関連の審査やコンサル、などの情報に明るく、要件に応じて、弊社コンサルティングサービスにも参加。2021年4月より、業界誌(月刊消費者信用)にてコラム「セキュリティ考現学」を寄稿中。
- トピックス:
- セキュリティ
- 関連トピックス:
- リスク管理