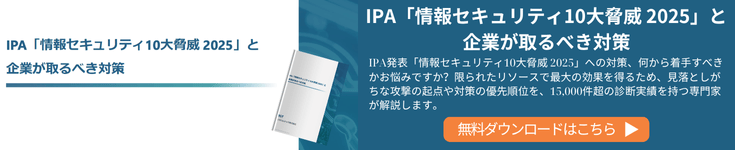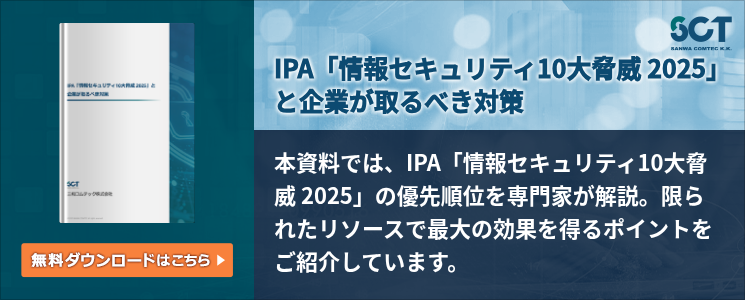サイバー攻撃はますます高度化しており、地政学的リスクが引き金となる攻撃が増加しています。国家間の緊張や対立はサイバー空間にも波及し、企業にとって重大な脅威です。本記事では、地政学的リスクが企業の情報セキュリティに与える影響と、その対策方法について解説します。最新の脅威動向や実践的な対策を知り、企業の防御体制強化に活用しましょう。
地政学的リスクとサイバー攻撃の関係

地政学的リスクとは、国際的な政治や経済の不安定性が引き起こすリスクを指します。特にサイバー攻撃の分野では、国家間の対立や不安定な政治情勢が深く関与しており、国際的な緊張の高まりとともにサイバー空間での攻防が激化しています。その結果、企業や政府機関は標的型攻撃や情報漏えい、インフラ破壊といった多様なサイバー脅威に直面しています。
地政学的リスクとは何か
地政学的リスクとは、国家間の対立や戦争、政変、経済制裁など、国際的な政治・経済の不安定性によって生じるリスクを指します。これらのリスクは、国境を越えてサプライチェーンやエネルギー供給、金融市場、そして近年ではサイバー空間にまで影響を及ぼします。
企業活動に与える影響は大きく、突然の輸出入制限や通信遮断、サイバー攻撃による被害など、想定外の事態に備えた対応が求められます。国際情勢の変化を的確に把握し、地政学リスクを経営課題として捉える姿勢が、今後ますます重要になっています。
国家主導のサイバー攻撃が増加する背景
地政学的リスクが高まる中、国家主導のサイバー攻撃が増加傾向にあります。国家間の対立や紛争が激化すると、サイバー攻撃は武力を伴わない政治的・経済的な手段として多用されるようになります。
特に、敵対国の重要インフラを標的とすることで、経済活動の混乱や社会不安を引き起こすことが目的とされます。攻撃者は政府機関や大企業の情報システムを狙い、機密情報の収集や経済的利益の獲得を図ります。
このようなサイバー攻撃は、従来の軍事行動に代わる「非対称的な圧力手段」として位置づけられ、企業の情報セキュリティにも深刻な影響を及ぼします。企業はこうしたリスクに備え、最新のセキュリティ対策を継続的に強化していくことが求められます。
注目されるインフラと産業分野
前述のとおり、地政学的リスクが高まる中で、特にサイバー攻撃の標的となりやすいインフラや産業分野として以下が挙げられます。
- エネルギー業界
電力網、石油・ガス供給網
攻撃時の影響:経済活動・市民生活への甚大な影響 - 通信インフラ
インターネット、電話通信システム
攻撃時の影響:情報流通停止、社会全体の混乱 - 防衛産業
機密情報、システム
攻撃時の影響:国家安全保障への直接的脅威 - 製造業
自動車産業、航空機産業
攻撃時の影響:知的財産の漏えい、技術流出
これらの分野は特にセキュリティの強化が求められます。
情報セキュリティ10大脅威 2025に見る影響

「情報セキュリティ10大脅威 2025」は、今後の情報セキュリティの脅威を予測する重要なレポートです。このレポートは、企業や政府機関に向けてリスクを早期に認識させ、対策を講じるための指針となります。
ここでは、2025年版にランクインした脅威に焦点を当て、その意味と企業への影響を分析します。
「情報セキュリティ10大脅威 2025」での位置づけとその意味
IPA(情報処理推進機構)が毎年発表している「情報セキュリティ10大脅威 2025」では、地政学的リスクに起因するサイバー攻撃が初めてランクインし、業界内で大きな注目を集めています。
この種の攻撃は、国家間の対立や政治的不安定を背景に、企業や重要インフラが標的となる点に特徴があります。今回の位置づけは、サイバー攻撃が単なる犯罪行為の域を超え、国際政治・経済に影響を与える戦略的手段としての側面を強めていることを明確に示しています。
企業にとっては、従来のセキュリティ対策に加え、地政学的な視点を取り入れた脅威対策が求められる時代に突入したといえるでしょう。
過去からの変遷と日本国内の対応
日本における情報セキュリティの対応は、年々進化しています。
初期段階では、企業単位での対策が主流でしたが、サイバー攻撃の規模や手法の高度化に伴い、政府も積極的に関与するようになりました。
特に、2014年に施行されたサイバーセキュリティ基本法により、官民一体でのセキュリティ強化が進みました。近年では、地政学的リスクに基づいたサイバー攻撃の脅威が増加し、政府はさらにセキュリティインフラの強化や国際的な連携を強化しています。企業も、独自のセキュリティ対策を進化させ、情報共有や協力体制の構築が重要視されています。
レポートから読み取れる企業への警鐘
IPAの「情報セキュリティ10大脅威 2025」レポートは、企業に対して強い警鐘を鳴らしています。特に、サプライチェーン攻撃や標的型攻撃が急増しており、従来の防御対策だけでは十分とはいえません。
企業は、自社のみならず取引先や業務委託先、外部ベンダーなどを含めた広範囲なセキュリティ対策が求められています。加えて、国家主導型のサイバー攻撃が増加しているため、情報収集や脅威インテリジェンスの強化が不可欠です。
企業は、リスクを正確に認識し、迅速にインシデント対応できる体制を整えることが重要です。
他国との比較:グローバルなリスク意識
他国では、地政学的リスクに基づくサイバー攻撃への対応が進んでおり、特にアメリカやヨーロッパでは、国家主導型の攻撃に対する警戒が強まっている状況です。
これらの国々では、情報セキュリティ政策が高度化しており、官民一体の対応や国際的な情報共有が積極的に行われています。
例えば、アメリカはサイバー攻撃に対して軍事的な報復を示唆するなど、リスクに対する厳格な姿勢を見せています。
一方、日本はこれらの取り組みに遅れを取っているとの指摘もあり、グローバルなリスク意識を高めるためには、他国との連携や国際標準に準じたセキュリティ対策の強化が求められます。
地政学的リスクによるサイバー攻撃の事例

地政学的リスクが高まる中、サイバー攻撃は企業や政府機関にとって深刻な脅威です。国家間の対立や政治的不安定さがサイバー攻撃を引き起こし、経済や社会への影響を拡大させています。ここでは、国内外で発生した標的型攻撃の事例について解説します。
国内外の標的型攻撃ケース
近年、国内外で国家間の緊張を背景にした標的型攻撃が急増しています。
特に、政治的な対立が激化する地域では、政府機関やシンクタンク、企業が攻撃のターゲットとなることが多くなっています。
近年、各国のシンクタンクや政治関係者、メディア関連組織に対して、地政学的対立を背景とした標的型攻撃の報告が相次いでいます。これらの攻撃は、情報収集や政治的な圧力をかける目的で行われ、企業にとっても自社データや顧客情報が漏えいするリスクにつながります。
国内外の政府機関も、こうした攻撃に備えた対策を強化していますが、依然としてリスクは高い状況です。
業界別に見た影響と傾向
地政学的リスクに起因するサイバー攻撃は、特定の業界において特に深刻な影響を及ぼしています。
エネルギー、通信、防衛、金融など、社会基盤を支える重要インフラ関連の業界は、攻撃の標的となりやすい傾向があります。
例えばエネルギー業界では、電力網やガス供給システムが攻撃されることで、経済活動の混乱や市民生活への影響が拡大しています。また金融業界では、銀行や決済システムが狙われるケースが多く、巨額の経済的損失や信用不安を引き起こすリスクがあります。
通信業界では、通信網の停止や情報漏えいが深刻な課題とされ、特に政府機関や防衛関連の情報が流出した場合は、国家安全保障にも直結する重大な事態となりかねません。
マルウェア・ランサムウェアの利用傾向
地政学的リスクに基づくサイバー攻撃で増加しているのは、マルウェアやランサムウェアの使用です。
特にランサムウェアは、重要な企業データを人質に取る手法として、脅威の一環として広く使われています。攻撃者が企業のシステムに侵入し、データを暗号化した後、その解除のために巨額の金銭を要求するという手法です。これにより、企業は経済的な損失だけでなく、顧客やパートナーからの信頼を失うリスクも抱えます。
さらに、国家が関与するサイバー攻撃では、ランサムウェアが政治的な圧力手段として使われる場合もあります。
情報漏えいや信頼低下がもたらす企業被害
サイバー攻撃による情報漏えいやデータ損失は、企業にとって深刻な経営リスクとなり得ます。
特に、顧客情報や知的財産の漏えいは、企業の信用を著しく損ない、結果として売上の減少や市場シェアの縮小といった実害につながるケースが少なくありません。
例えば、大手企業がサイバー攻撃を受け、顧客データが流出した場合には、顧客離れに加え、法的責任や多額の賠償金支払いなど、経済的・社会的影響が長期化する可能性があります。
さらに、一度失ったブランドイメージを回復するには多大な時間とコストを要するため、迅速な対応とともに信頼回復に向けた戦略的な取り組みが不可欠です。
サプライチェーン攻撃のリスク
近年増加しているサプライチェーン攻撃とは、企業が利用・連携している外部の取引先やサービスプロバイダーなどを経由して行われるサイバー攻撃です。
攻撃者は、取引先やサービスプロバイダーのセキュリティの脆弱性を突き、そこを足がかりに標的企業のネットワークへ侵入し、機密情報を窃取するケースがあります。
この攻撃手法の特徴は、企業への直接攻撃ではなく、信頼された外部パートナーを経由することで防御の目をかいくぐる点にあります。そのため、企業は攻撃リスクを即座に把握しにくく、兆候の見落としにもつながりやすいのが現状です。
こうした脅威に対処するためには、自社だけでなくサプライチェーン全体のセキュリティ強化が不可欠です。パートナー企業との情報共有やリスク対応体制の構築を進め、全体としての防御力を高めることが求められます。
企業が講じるべき情報セキュリティ対策

地政学的リスクに関連するサイバー攻撃が増加する中で、企業が講じるべき情報セキュリティ対策はますます重要です。ここでは、リスク評価、体制強化、技術的対策、教育、外部との連携に焦点を当て、企業が取るべき具体的な対策を紹介します。
リスク評価の導入と脅威インテリジェンスの活用
企業がサイバー攻撃に備えるためには、まず自社のリスクを正確に評価することが重要です。リスク評価により、どの部門や資産が最も脆弱であるかを特定し、優先的に対策を講じることができます。
脅威インテリジェンス(脅威情報)を活用することで、最新の攻撃手法や脅威情報を把握し、即座に対応する準備を整えることが可能です。
脅威インテリジェンスは、外部のサイバー脅威の動向を把握するために役立ち、企業が攻撃を受ける前に防止策を講じるための重要な情報源となります。
企業は、リスク評価と脅威インテリジェンスの活用を通じて、攻撃のリスクを最小化できます。
体制づくりと平時からの備えを強化する方法
サイバー攻撃に対する備えは、平時から強化することが重要です。
企業は、インシデントが発生した際に迅速に対応できる体制を整える必要があります。
これには、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)やBCP(Business Continuity Plan)などの組織的な準備が不可欠です。
また、定期的な演習やシミュレーションを行い、インシデント対応のスキルを向上させることも重要です。
平時からの備えを強化することで、実際の攻撃が発生した際のダメージを最小限に抑えることができます。
多層防御やゼロトラストによる技術的な対策
サイバー攻撃に対する防御は、技術的な対策が欠かせません。
多層防御を導入することで、攻撃者が一度の突破で企業のシステムにアクセスするリスクを減らすことができます。
例えば、ファイアウォール、アンチウイルスソフト、侵入検知システムなど、複数の防御層を組み合わせることで、攻撃の検出と防止が可能です。
また、ゼロトラストは、内部ユーザーでもアクセス権を最小限に抑え、常に信頼性を確認することで攻撃を防ぎます。
このような技術的対策は、企業のセキュリティ体制を大きく強化し、サイバー攻撃に対する耐性を高めることができます。
従業員と経営層の意識を高めるための教育
情報セキュリティにおいて、従業員と経営層の意識向上が非常に重要です。
従業員は企業のセキュリティ対策を最前線で実行するため、セキュリティ教育を定期的に実施し、フィッシング攻撃やマルウェアに対する認識を高めることが求められます。
また、経営層は情報セキュリティを重要な経営課題として位置づけ、十分なリソースを確保する必要があります。意識向上のためには、セキュリティに関する最新情報や攻撃手法の教育を通じて、従業員と経営層が一体となって企業全体で情報セキュリティの強化を図ることが必要です。
外部との連携によるセキュリティ体制の強化
企業のセキュリティ体制は、外部との連携を強化することで一層強固なものになります。
業界団体や政府機関、情報セキュリティ企業と連携し、情報共有や協力体制を構築することで、リアルタイムで脅威情報を交換できます。
サプライチェーン攻撃に備えるためには、取引先やパートナー企業とのセキュリティ協力も不可欠です。また、国際的なセキュリティ基準や規制に従い、グローバルなリスクに対処するための体制を整えることも重要です。
外部との連携を通じて、企業は脅威に対する即応力を高め、セキュリティ体制をさらに強化できます。
継続的な備えと見直しの必要性

サイバー攻撃の脅威は進化し続けており、企業はその変化に対応するために継続的な備えと見直しを行う必要があります。ここでは、実践的な演習や脅威動向のモニタリング、内部監査、そしてセキュリティ文化の定着といった重要な対策を解説します。
実践的な演習による対応力の向上
サイバー攻撃に迅速に対応するためには、実践的な演習を行うことが不可欠です。
企業は定期的にインシデント対応のシミュレーションを実施し、実際に攻撃を受けた際に迅速かつ効果的に対応できる体制を整えます。
こうした演習は、従業員の対応スキルを向上させるとともに、セキュリティチームが実際のシナリオでどのように行動すべきかを確認するための重要な手段です。
さらに、演習を通じて発見された改善点を反映させ、セキュリティ体制の強化を図ることが求められます。
脅威動向のモニタリングと定期更新
サイバー攻撃の手法は日々進化しています。
企業は最新の脅威動向をモニタリングし、継続的にセキュリティ対策を更新することが必要です。
脅威インテリジェンスを活用し、攻撃者の新たな手法や動向を把握することで、企業は即座にリスクに対応できる体制を整えます。定期的なパッチ適用やシステムの更新を行うことも、既知の脆弱性を狙った攻撃から企業を守るためには欠かせません。常に情報をアップデートし、最新の脅威に備えることが求められます。
内部監査と外部評価の活用
企業のセキュリティ体制を効果的に強化するためには、内部監査と外部評価の活用が重要です。
内部監査は、社内のセキュリティ対策が適切に実行されているかを確認するプロセスであり、脆弱性や改善点を早期に発見できます。また、外部評価は第三者の視点から企業のセキュリティ体制を検証し、客観的な改善点を指摘してもらうことが可能です。
ペネトレーションテストやセキュリティ監査を通じて、より高いセキュリティレベルを確保し、攻撃に対する耐性を向上させることができます。
セキュリティ文化の定着
情報セキュリティは技術的な対策だけでなく、企業文化として定着させることが重要です。
従業員全員がセキュリティ意識を持ち、日常的に適切な行動を取ることが、企業のセキュリティ体制を支える基盤となります。定期的なセキュリティ教育やトレーニングを通じて、従業員に最新の脅威や攻撃手法を理解させ、適切な対策を講じる力を養います。
また、経営層が積極的にセキュリティ意識を高め、組織全体でそれを重視する文化をつくり上げることが、企業全体のセキュリティ強化につながります。
まとめ
地政学的リスクに起因するサイバー攻撃は企業にとって重大な脅威であり、適切な対策を講じることが不可欠です。リスク評価、技術的対策、従業員教育、外部との連携を強化し、常に最新の脅威に対応できる体制を築くことが求められます。
企業は、継続的な備えと見直しを行い、サイバー攻撃の影響を最小限に抑えることが重要です。このような取り組みを通じて、企業のセキュリティ体制を強化し、リスクを管理することが可能となります。
三和コムテックでは、情報セキュリティの脅威に対して企業が取るべき対策を公開しています。地政学的リスクを含め、情報セキュリティの脅威とその対策について分かりやすく解説していますので、ぜひご確認ください。
セキュリティソリューションプロダクトマネージャー OEMメーカーの海外営業として10年間勤務の後、2001年三和コムテックに入社。
新規事業(WEBセキュリティ ビジネス)のきっかけとなる、自動脆弱性診断サービスを立ち上げ(2004年)から一環して、営業・企画面にて参画。 2009年に他の3社と中心になり、たち上げたJCDSC(日本カードセキュリティ協議会 / 会員企業422社)にて運営委員(現在,運営委員長)として活動。PCIDSSや非保持に関するソリューションやベンダー、また関連の審査やコンサル、などの情報に明るく、要件に応じて、弊社コンサルティングサービスにも参加。2021年4月より、業界誌(月刊消費者信用)にてコラム「セキュリティ考現学」を寄稿中。
- トピックス:
- セキュリティ
- 関連トピックス:
- リスク管理