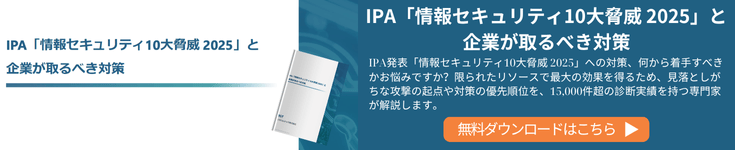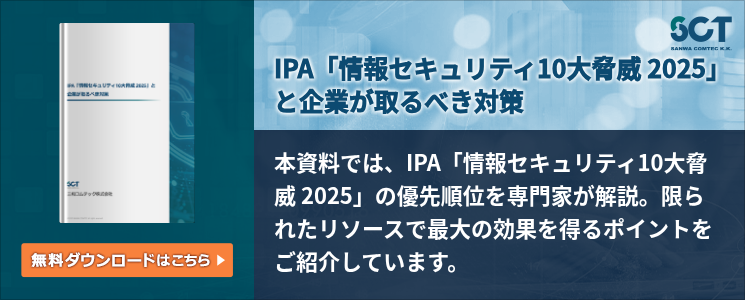「地政学的リスクとはどんなリスクか」
地政学的リスクは国家間の緊張や対立など、地理的・政治的な背景から生じる不確実性の高いリスクのことです。国家間と聞き、自社は無関係と考えるかもしれませんが、巻き込まれる可能性は十分にあり、他人事ではありません。
本記事で地政学的リスクの基本的な意味と、具体的なリスク、企業としてできる対策などを確認してください。
地政学的リスクの基本的な意味

まず、「地政学」とは、国家の地理的な位置関係、資源の有無、周辺国との関係性などをもとに、その国や地域の安全保障や国際関係を分析する学問です。例えば、資源が豊富な国や戦略的に重要な地域に位置する国は、他国との摩擦や干渉が生じやすいとされます。これは地政学的観点から説明できる典型例です。
この「地政学」の視点をビジネスや経済活動に応用した概念が、「地政学的リスク」です。近年、以下のような要素がリスク要因として注目されています。
- 戦争や武力衝突
- 領土・領海をめぐる緊張
- テロリズムの脅威
- 経済制裁
- 政情不安や政権交代 など
現代のグローバル経済においては、一国の不安定な状況がサプライチェーン全体や国際市場に波及する可能性があります。そのため、企業は地政学的リスクの特性を正しく理解し、予測・回避・分散といった対応策を講じることが不可欠です。
地政学的リスクの主な要因

地政学的リスクの主な要因として以下があります。
- 紛争や戦争
- 国際的な経済制裁
- テロや政情不安
- 海峡封鎖や物流ルートの遮断
紛争や戦争
地政学的リスクとして真っ先に思いつくのが紛争や戦争による武力衝突です。
武力衝突が起きると、国家間の緊張は一気に高まり、周辺地域の経済活動や資源供給が大きく妨げられます。例えば、ロシアによるウクライナ侵攻は、欧州全体のエネルギー供給に混乱を引き起こし、食料や燃料価格の高騰にもつながりました。中東における度重なる武力衝突も、世界的な原油価格に大きな影響を与えています。
紛争や戦争は経済活動にも大きな影響を与えるため、ビジネスや投資のリスクとして常に注視されています。
国際的な経済制裁
国際的な経済制裁も、地政学的リスクの1つです。
経済制裁は主に外交政策の一環として実施され、対象国の金融システムや貿易活動に深刻なダメージを与えます。国家による侵略行為や人権侵害、核開発など、秩序に反する行為があった際に、制裁対象国が課されるものです。
また制裁は特定の企業や産業にも適用されるため、対象国との取引を行っている企業は、業務停止や契約破棄などのリスクがあります。制裁が長期化すると、サプライチェーンの断絶や株価、商品価格の乱高下といった連鎖的な影響が世界経済に及びます。
テロや政情不安
テロ行為や政情不安は、企業活動や投資判断において重大な地政学的リスクとなります。
クーデターや政権交代による急激な政策変更、あるいは治安の悪化が頻発する地域では、事業の継続が困難になることも少なくありません。そのため、撤退や新規投資の見直しといった判断を迫られるケースが多くなります。
実例としては、ミャンマーでのクーデターやアフガニスタンにおけるテロの頻発などが挙げられます。
特に新興国では、こうしたリスクが直接的に事業継続に影響を及ぼすため、慎重な対応が求められます。
不安定な地域に進出する際は、現地の政治・治安状況を十分に調査し、有事の際にも事業を継続できる体制を整えておくことが不可欠です。
海峡封鎖や物流ルートの遮断
グローバルなサプライチェーンにおいて、海峡などの物流ルートが封鎖されることは重大な地政学的リスクです。
戦略的に重要な輸送路が軍事的・政治的な理由で遮断されると、エネルギー資源や原材料の供給が滞ります。結果として、商品価格の高騰や供給不足につながるでしょう。
例えば、ホルムズ海峡が封鎖されれば中東の原油輸送に大きな影響が出ますし、台湾海峡の緊張は半導体などの重要産業への供給リスクを高めます。
物流ルートの安定性確保は企業経営や商品の安定供給に直結する重要な課題です。
地政学的リスクがビジネスや投資に与える影響

地政学的リスクがビジネスや投資に与える影響として以下があります。
- サプライチェーンの混乱
- 原材料やエネルギー価格の高騰
- 海外進出企業のリスク管理
- 投資先・資産運用向け選択の難化
サプライチェーンの混乱
地政学的リスクが与える最も顕著な影響の1つがサプライチェーンの混乱です。
紛争や経済制裁、海峡封鎖により、輸送ルートが断たれると、必要な部品や原材料の調達が困難になります。生産活動に支障をきたす事態に陥るでしょう。特に製造業では、納期の遅延や代替調達によるコスト増加が発生し、企業の競争力に直結します。
サプライチェーンの混乱は企業の安定性に直結するため、早急なリスク対策が必要です。
原材料やエネルギー価格の高騰
地政学的な緊張が高まると、原材料やエネルギー価格にも深刻な影響が及びます。
紛争や経済制裁、海峡の封鎖といった事態は、サプライチェーンの混乱に加え、資源価格の急激な変動を引き起こす要因となります。
特に日本は、資源の多くを海外からの輸入に依存しているため、その影響を受けやすい国といえるでしょう。
例えば、産油国で政情不安が発生した場合、原油や天然ガスの供給が滞り、価格の高騰は避けられません。その結果、製造業や物流業など多くの産業においてコストが上昇し、利益率が圧迫されます。
企業の工夫や効率化では吸収しきれない水準までコストが膨らむケースもあり、地政学的リスクの影響の大きさを痛感させられる事態に発展することもあります。
海外進出企業のリスク管理
地政学的リスクは、海外に進出している企業の経営にも影響します。
進出先の国で政情不安や通商リスクが高まれば、現地法人の事業継続は困難です。実例として、ミャンマーでは2021年のクーデター後、多くの外国企業が安全確保や将来性への不安から事業を縮小・撤退しました。ベネズエラでは政治混乱と経済崩壊により、現地での通貨取引や送金が困難となり、外資企業が次々と撤退しています。
企業は政治リスク保険の導入や撤退を判断する基準の事前整備など、地政学的リスクの対策をしておく必要があります。
投資先・資産運用向け選択の難化
投資や資産運用においても、地政学的リスクは無視できません。
対象地域の緊張が高まると、関連する企業の株価や通貨、債券価格などが不安定になります。この不安定さにより投資対象としての魅力低下は避けられません。また情勢の急変で、想定外の損失が発生するリスクもあります。例えば、ロシアのウクライナ侵攻以降、多くの投資家がロシア市場から撤退し、ルーブルやロシアの株式市場は大きく下落しました。
投資家はリスク分散の重要性が増し、ポートフォリオの見直しや情報収集をする必要があります。
地政学的リスクの具体例

地政学的リスクの具体例として以下があります。
- ロシア・ウクライナ戦争によるエネルギー供給不安
- 米中関係と経済的リスク
- 中東地域の政情不安と原油市場の変動
- 台湾情勢と半導体サプライチェーンのリスク
- 国家間の対立によるサイバー攻撃の増加
ロシア・ウクライナ戦争によるエネルギー供給不安
2022年に始まったロシアのウクライナ侵攻は、欧州を中心に大きな混乱をもたらしています。
この紛争により天然ガスや原油などのエネルギー供給が大きく揺らぎ、エネルギー価格の急騰を引き起こしています。欧州諸国はロシアへのエネルギー依存を減らすために調達先を多様化させました。しかし、その影響は国際市場全体に及び、日本を含む多くの国で電力料金や物流コストの上昇を招いています。
また各国はロシアへの経済制裁として、金融・輸送など幅広い分野で取引を制限しました。これにより、2025年現在も投資家による判断の変更や、企業によりさまざまな物流ルートの変更が避けられない状況です。
企業活動にも多大な影響を与え、各国の企業は収益構造の見直しを迫られています。
米中関係と経済的リスク
米中関係は、21世紀を通じて国際政治および経済における最重要リスクの1つとされています。
近年では、テクノロジー分野や安全保障、貿易政策をめぐる対立が激化しており、米国は中国企業に対して輸出規制や投資制限を強化しています。一方の中国も、自国経済を防衛するため、さまざまな対抗措置を講じており、両国関係は「新冷戦」とも呼ばれる緊張状態にあります。
さらに、米国でトランプ氏が大統領に再就任して以降、中国への対応は一層強硬な姿勢を示しています。このような米中対立の長期化は、両国と経済的に結びつきの強い日本企業にも直接的な影響を及ぼします。サプライチェーンの再構築や市場戦略の見直しを余儀なくされる場面も増えており、今後の動向に対する継続的な注視と柔軟な対応が求められます。
中東地域の政情不安と原油市場の変動
中東地域では、国家間の緊張が続いており、これが原油価格の乱高下を招いています。
具体的な国家名を挙げると、イラン、イスラエル、パレスチナ、サウジアラビアなどです。
例えば、イラン核合意の不透明さやイスラエルとハマスの武力衝突などは、原油の供給不安を引き起こし、国際市場に動揺を与えています。トランプ大統領による決断でイランを空爆し、核開発へ待ったをかける動きなども見られました。
原油は世界の経済活動にとって不可欠な資源です。そしてエネルギー輸入に依存している日本は、この地域の政情不安は重大なリスクとなります。物流網の安定性やエネルギー安全保障の観点からも、注視が必要です。
台湾情勢と半導体サプライチェーンのリスク
台湾情勢と半導体サプライチェーンのリスクも日本企業にとっては見逃せない地政学的リスクです。
台湾は、世界の半導体製造において重要な役割を担っています。高度な製造能力と技術力を有しており、世界の先端企業が必要とする半導体製造を引き受けているためです。
しかし、中国との政治的緊張が高まる中で、台湾情勢はアジア地域の安全保障の不安定要因となっています。もし中国が台湾に対して軍事的行動を取るような事態が起これば、半導体の供給が途絶えることになるでしょう。これは、テクノロジー産業のみならず、自動車や家電などあらゆる製造業に深刻な打撃を与えます。
半導体以外の面でも、日本は台湾と地理的にも経済的にも密接な関係にあり、巻き込まれる可能性が高いため、企業はリスクへの備えを強化する必要があります。
国家間の対立によるサイバー攻撃の増加
サイバー空間は目に見えない新たな戦場となっており、サイバー攻撃の増加も大きな地政学的リスクです。
地政学的な緊張が高まると、軍事的な衝突に先立ってサイバー空間での攻撃が行われることが多くあります。国家が主導するサイバー攻撃は、政府機関や重要インフラ、民間企業を標的にし、情報漏えいやシステム障害、社会的混乱を引き起こすものです。物理的な戦争と同様、もしくはそれ以上に長期的かつ甚大な被害を与える可能性もあります。
国家主導型のサイバー攻撃、いわゆるAPT(Advanced Persistent Threat)攻撃が増加しています。APT攻撃は、高度な技術と長期的な戦略に基づいて行われ、検知や防御が非常に難しいことが特徴です。
例として以下のAPT攻撃がありました。
- ロシアのAPTグループ「APT28(Fancy Bear)」による米大統領選関連機関への侵入
- 中国の「APT10」によるグローバル企業への知的財産窃取
サイバー攻撃対策として、情報セキュリティの強化やインシデント対応体制の整備が必要です。
企業が受けるサイバー攻撃のリスク

国家間の対立によるサイバー攻撃について解説しましたが、民間企業がサイバー攻撃を受けるリスクも十分にあります。以下の観点で解説します。
- 一般的に狙われる企業の特徴
- 地政学的リスクにより狙われる企業もある
一般的に狙われる企業の特徴
サイバー攻撃の標的となりやすい業種には、金融、エネルギー、通信、製造業などの重要インフラ関連企業が含まれます。
これらの業種は社会インフラの中核を担っており、万が一攻撃を受けると、その影響は広範囲に及びます。国家全体に混乱をもたらしたい攻撃者や、高額な成功報酬を狙うサイバー犯罪者にとっては、格好のターゲットといえるでしょう。
加えて、近年ではサプライチェーンを介した攻撃も増加傾向にあります。大企業や政府機関は高度なセキュリティ体制を整備している場合が多い一方で、取引先や下請け企業まで同水準の対策が講じられているとは限りません。こうした「セキュリティのすき間」を突くのが、サプライチェーン攻撃の特徴です。セキュリティが手薄な関連企業を足がかりに、本来の標的へと侵入を試みる手法が多く見られます。
情報処理推進機構(IPA)が発表した「情報セキュリティ10大脅威2025」でも、サプライチェーン攻撃は第2位にランクインしています。脅威が現実化している今、中小企業であっても油断は禁物です。規模にかかわらず、自社と取引先双方のセキュリティ強化が欠かせません。
地政学的リスクにより狙われる企業もある
地政学的リスクにより狙われる企業もあります。
特定の国や地域に関連する企業は、国際的な緊張関係に巻き込まれる形で標的となるケースがあります。例えば、防衛、エネルギー、通信などの重要インフラを担う企業や、政府機関と取引を行っている企業は、国家主導型のAPT攻撃を受けるリスクが高いです。
2025年1月に警察庁及び内閣サイバーセキュリティーセンターが注意喚起している、中国の関与が疑われるMirrorFace攻撃があります。関連する個人や組織に対して悪質なプログラムを添付したメールを送信し、情報窃取を試みるサイバー攻撃を仕掛けた攻撃です。
国家間の関係とはいえ、民間企業でもAPT攻撃を受けるリスクがあるため、対策が必要です。
企業による地政学的リスクへの対応

企業による地政学的リスクへの対応として以下があります。
- リスクマップの作成と定期的な見直し
- サプライチェーンの多元化
- 情報収集体制の強化
- 政治リスク保険の活用
- BCP(事業継続計画)の見直し
リスクマップの作成と定期的な見直し
自社が直面する地政学的リスクを把握する上で、リスクマップの作成は欠かせません。影響度や発生確率を可視化することで、対策の優先順位が明確になります。
完成したマップをもとに、例えば紛争リスクの高い地域に拠点がある場合は、以下のような具体策を検討すると効果的です。
- 代替拠点の候補検討
- 早期警戒体制の構築
- 事業継続計画(BCP)の見直し
国際情勢は日々変化するため、リスクマップは「作って終わり」では役に立ちません。以下のタイミングで見直しを行い、最新情報を反映させましょう。
- 新たな地政学的リスクが顕在化したとき
- 事業拠点やサプライチェーンに変更があったとき
- 定期(半年〜年)でのレビュー
これらのサイクルを回すことで、自社のリスクプロファイルを常に最新の状態に保ち、迅速な対応を実現できます。結果として、地政学的ショックへの耐性が高まり、事業運営の安定化につながるでしょう。
サプライチェーンの多元化
サプライチェーンの多元化も地政学的リスクの対策として有効です。
調達先や生産拠点が特定の国や地域に偏っていると、その地域の政情不安や通商制限により、事業全体が大きな影響を受けてしまいます。また昨今のサプライチェーン攻撃の広まりから、自社以外が攻撃を受けた場合でも影響を避けられません。
対策として、複数の国や地域にサプライチェーンを分散することで、リスク発生時の影響を最小限に抑えられます。コスト面や事業、手続きの複雑さは増加しますが、長期的には事業の安定性と継続性の確保につながります。
情報収集体制の強化
信頼性の高い情報の収集も地政学的リスクの対策には不可欠です。
公開情報(OSINT:Open Source Intelligence)の活用は、コストを抑えつつ早期のリスク察知を可能にする手段となります。OSINTの情報源は外務省や国際機関、シンクタンク、ニュースメディアなどです。集める情報の例として、外交や安全保障情報、エネルギーの取得に関する情報などがあります。
OSINTにより得られたデータを分析し、社内で定期的にレポート化する体制を整えることで、判断のスピードと精度が高まります。情報収集の専任チームや外部専門家との連携も有効です。
政治リスク保険の活用
予測不能な地政学的リスクに備える手段として、政治リスク保険の活用が有効です。
国内への投資は事業の安定性や競合との関係を踏まえれば判断ができます。しかし、新興国や情勢が不安定な地域に投資する場合は、突発的な国有化、契約破棄、為替送金の制限、暴動による財産の損壊など、事業を脅かすリスクを避けられません。これらのリスクをカバーする保険で、万が一の事態でも損失を最小限に抑えられます。
政治リスク保険は民間保険会社や国際協力機関(例:日本貿易保険 NEXI)などが提供しており、事業内容や進出先の情勢に応じたカスタマイズも可能です。特に不安定な地域に進出する際には、リスクヘッジ手段の一つとして積極的に検討すべきといえます。
BCP(事業継続計画)の見直し
企業のBCPも、地政学的リスクを想定した内容に見直すべきです。
BCPには地震や自然災害などの対策やその際の計画が含まれるでしょう。しかし、政情不安や戦争、制裁などによって拠点が機能不全に陥る可能性もあるため、それらを含んだ計画へと見直し、非常時でも事業を止めないための計画を常に最新に保つ必要があります。
例として、通信手段の確保、代替拠点の準備、サプライヤーとの協力体制など、地政学的な不安定性を加味したシナリオを組み込み、具体的な対応策を事前に用意しておくことで、緊急時にも事業継続が可能です。訓練や見直しを定期的に行い、実効性のあるBCPとしましょう。
まとめ

地政学的リスクは地理的・政治的な背景から生じる不確実性の高いリスクのことであり、民間企業としても無視できません。特に近年は企業がサイバー攻撃を受けるリスクがあり、対策が不可欠となっています。
弊社では、「IPA 10大脅威 2025」をもとに、医療機関向けの解説と対策をまとめた資料をご用意しています。以下よりダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
セキュリティソリューションプロダクトマネージャー OEMメーカーの海外営業として10年間勤務の後、2001年三和コムテックに入社。
新規事業(WEBセキュリティ ビジネス)のきっかけとなる、自動脆弱性診断サービスを立ち上げ(2004年)から一環して、営業・企画面にて参画。 2009年に他の3社と中心になり、たち上げたJCDSC(日本カードセキュリティ協議会 / 会員企業422社)にて運営委員(現在,運営委員長)として活動。PCIDSSや非保持に関するソリューションやベンダー、また関連の審査やコンサル、などの情報に明るく、要件に応じて、弊社コンサルティングサービスにも参加。2021年4月より、業界誌(月刊消費者信用)にてコラム「セキュリティ考現学」を寄稿中。
- トピックス:
- セキュリティ
- 関連トピックス:
- リスク管理