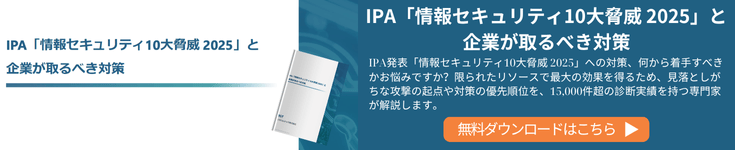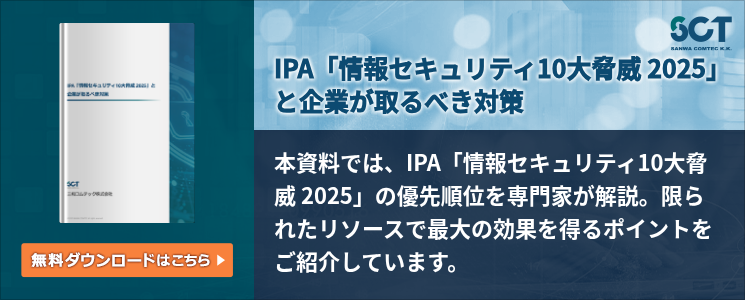病院を狙うサイバー攻撃は年々巧妙化しており、医療機関の重要なシステムがターゲットとなっています。電子カルテや診療機器への影響は深刻で、業務停止や情報漏洩を引き起こすリスクも高まっています。本記事では、病院におけるサイバー攻撃の最新動向とその対策について詳しく解説します。
病院を標的とするサイバー攻撃の最新動向

近年、病院をはじめとする医療機関はサイバー攻撃の格好のターゲットとなっています。
患者情報や診療データなど、病院のシステムは非常に価値が高く、悪意のある第三者に狙われる理由は明白です。中でもランサムウェアやフィッシング、DDoS攻撃といった手法が悪用されており、医療業務の停滞や患者の安全に直結する問題を引き起こしています。
なぜ医療機関が狙われやすいのか、具体的な背景を見ていきましょう。
病院が狙われる背景
病院はその業務特性から、多くの機微な情報を取り扱う組織です。
特に、患者の個人情報や診療履歴、医療機器の操作ログなどは、悪意のある第三者にとって非常に高い価値を持つ標的となります。さらに、病院では診療や手術などの業務継続性が最優先されるため、システムのダウンタイムが許容されにくいという特徴があります。このような性質が、攻撃者にとって「交渉材料になりやすい弱点」として悪用される要因となっています。
加えて、古いOSやアップデートが困難な医療機器が稼働し続けているケースが多く、セキュリティ対策が万全とは言い難い現場も少なくありません。こうした技術的な脆弱性もまた、サイバー攻撃を受けやすい要因となっています。
これらの背景が重なり合うことで、病院はサイバー攻撃者にとって非常に魅力的かつ侵入しやすい標的となっているのです。
病院固有のシステム的脆弱性
病院が抱えるシステム的な脆弱性は、主に以下のような要因に起因しています。
先述したように、病院では古い医療機器やシステムが運用されていることが多く、更新が後回しにされがちです。これらの機器には最新のセキュリティパッチが適用されていないケースがあり、攻撃者にとって侵入しやすい対象となっています。
加えて、病院では複数の異なるシステムが連携して動作しているため、セキュリティ管理が複雑化する傾向があります。
例えば、電子カルテシステム、放射線機器、院内のWi-Fiネットワークなどは、それぞれ異なるセキュリティ基準で運用されている場合があり、一部のシステムが突破されると、他のシステムへも連鎖的に侵入されるリスクが生じます。
さらに、職員のセキュリティリテラシーが不十分な場合、フィッシングやソーシャルエンジニアリングといった手口による侵害が起きやすくなります。このように、技術的な脆弱性と人的リスクが複合的に絡み合っているのが、病院の大きな課題です。
病院を襲うサイバー攻撃の手法

病院におけるサイバー攻撃は、ランサムウェア、標的型メール、DDoS攻撃など多岐にわたります。これらの攻撃手法は、病院の業務停止やデータ漏洩を引き起こし、患者の安全や信頼を大きく損なうことがあります。
ここでは、病院を狙う代表的なサイバー攻撃の手法について解説します。
病院を麻痺させるランサムウェア攻撃の脅威
ランサムウェア攻撃は、病院にとって最も深刻なサイバー攻撃の1つです。攻撃者は病院のシステムに侵入し、患者の診療データや電子カルテを暗号化した上で、その復旧と引き換えに金銭(身代金)を要求します。
このような攻撃により、診療業務が一時的に停止するケースも多く、患者の生命に直接影響を及ぼす可能性があります。単に治療の妨げとなるだけでなく、病院としての信頼性も大きく損なわれることになります。
病院がランサムウェアの標的となりやすい背景には、扱うデータの重要性と、業務停止による損失の大きさが関係しています。そのため、攻撃者は「身代金を支払ってでも業務再開を優先する」と見込んで攻撃を仕掛けてくるのです。
さらに、一度攻撃を受けた後の復旧作業には膨大な時間とリソースが必要となり、技術的・金銭的な負担も大きくなります。近年では、病院を狙ったランサムウェアの被害が世界中で相次いでおり、早急な対策の必要性が高まっています。
病院を狙う巧妙な標的型メールの手口
標的型メール攻撃は、病院をはじめとする多くの組織が被害を受けている代表的なサイバー攻撃手法の1つです。この手口では、攻撃者が医療従事者をターゲットにフィッシングメールを送り、リンクのクリックを誘導することでマルウェアを拡散させます。
特に医療現場では、日々の業務が多忙なことから、メールの確認がおろそかになりやすく、結果として攻撃のリスクが高まります。
標的型メールの多くは、実在の病院や取引先になりすました文面や、患者からの依頼に見せかけた内容を装っており、受信者に「信頼できる連絡だ」と思わせるよう巧みに設計されています。こうしたメールに含まれる不正リンクを開いてしまうと、マルウェアに感染し、院内システムの停止や機密情報の流出といった深刻な被害に発展する可能性があります。
標的型メールは「気付きにくい脅威」だからこそ、全職員への継続的な注意喚起と訓練が不可欠です。
診療業務を停止させるDDoS攻撃
DDoS(分散型サービス拒否)攻撃は、病院のインターネットサービスや外部との通信を遮断することを目的としたサイバー攻撃です。攻撃者は大量のトラフィックを一斉に病院のサーバへ送りつけ、システムを過負荷に陥らせて機能不全に追い込みます。
この結果、電子カルテの閲覧や予約システムの利用、患者情報へのアクセスが一時的に不可能になるといった事態が発生し、診療業務が深刻な影響を受けます。
DDoS攻撃による業務停止は、患者への対応が遅れるなど、命に関わるリスクにも直結するため、病院にとって重大な脅威です。
また、復旧には時間的・金銭的コストが大きくかかることから、事前に防御体制を整えておくことが不可欠です。
病院へのサイバー攻撃の被害事例

病院はサイバー攻撃の標的となりやすく、その被害は診療業務の停止や患者データの流出など、医療提供体制に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、実際に発生した病院へのサイバー攻撃事例を取り上げ、被害の内容やそこから得られる教訓について解説します。
電子カルテが使用不能となった地方病院の事例
2023年、国内の地方病院がランサムウェア攻撃を受け、電子カルテシステムが使用不能となる事態が発生しました。攻撃者は病院ネットワークに侵入し、患者データを含む重要なファイルを暗号化。これにより、病院の診療業務に深刻な支障が生じました。
病院側は業務の継続を最優先したものの、完全な復旧には約2カ月を要し、その間電子カルテへのアクセスはできない状態が続きました。診療は手書き記録や紙ベースでの運用に切り替えられ、患者への影響や医療ミスのリスクが懸念されました。
さらに、一部の治療情報が失われたことで、診療の遅延や再診対応を余儀なくされたケースも報告されています。
攻撃後、病院は外部のセキュリティ専門家を招き、システムの再評価および対策の強化を実施しています。この一件は、病院にとってサイバーリスク対策の必要性を再認識させる重要な教訓となりました。
医療機器が停止した大学附属病院の事例
2022年、ある大学附属病院がランサムウェア攻撃を受け、診療に不可欠な医療機器が一時的に停止しました。攻撃者は院内ネットワークへ侵入し、複数の機器に関連するデータを暗号化したと見られています。
特に影響を受けたのは、放射線機器やCTスキャナーなどの高額かつ高機能な装置です。これらが使用不能となったことで、患者の診断に遅延が発生し、緊急を要するケースでは医療行為に深刻な支障が出ました。一部の患者には、再診や画像の再取得が必要となるなどの対応も求められました。
復旧作業の期間中、病院では一部業務を手作業に切り替えて診療を継続しましたが、通常の効率を大きく下回る状態が続きました。また、データの回復には多大な時間と人的リソースが必要となり、財務面への負担も無視できない規模となりました。
この事例は、医療機器に対するサイバーセキュリティ対策が、診療体制そのものを守るために不可欠であることを改めて示しています。
診療データが暗号化された市立病院の事例
2021年、ある市立病院がランサムウェアに感染し、診療データが暗号化される被害に遭いました。攻撃者は内部ネットワークへ侵入し、患者の個人情報や診療歴など重要なデータを狙ったとされています。
診療に不可欠な情報が利用できなくなったことで、一時的に手作業による対応を余儀なくされ、治療の遅延が生じる場面も見受けられました。特に緊急手術を必要とする患者への対応が遅れたことで、生命にかかわるリスクが高まったことが懸念されました。
復旧には数週間を要し、その間、病院の信頼は大きく揺らぐ結果となりました。社会的影響も無視できず、この事件は医療現場のサイバーセキュリティの脆弱性を改めて浮き彫りにしました。
以降、病院ではセキュリティ強化とバックアップ体制の見直しを急ぎ、データ保護の重要性と早期復旧の体制構築がいかに不可欠かを深く認識することになりました。
病院が取り組むべきサイバーセキュリティ対策

病院におけるサイバー攻撃は、患者の命に直結するリスクを伴います。
そのため、病院は高度なセキュリティ対策を導入し、予防と早期発見、迅速な対応ができる体制を整えることが不可欠です。
具体的な対策として、多層防御やスタッフ教育、インシデント対応体制の構築が求められます。さらに、システムの定期的なバックアップや脆弱性診断を行い、攻撃の兆候を早期に察知して迅速に対応することが重要です。
ここでは、病院が取り組むべき具体的なサイバーセキュリティ対策について解説します。
病院における多層防御の構築方法
多層防御は、複数の防御層を設け、攻撃を段階的に阻止する方法です。病院におけるサイバー攻撃に対して、1つの防御策に頼るだけでは不十分です。
まずは、ファイアウォールやマルウェア対策ソフトなどの基本的なセキュリティツールを導入し、外部からの不正アクセスを防ぎます。その後、内部ネットワークをセグメント化して、万が一システムが侵害されても被害を最小限に抑えます。医療機器やシステムには、定期的にセキュリティパッチを適用し、最新の脅威に対応することが不可欠です。
加えて、強固な認証システムや二要素認証を導入することで、内部からの不正アクセスを防げます。
このように多層防御を実施することで、攻撃者が1つの防御層を突破しても、他の層で防げる可能性が高くなります。
医療スタッフのセキュリティ意識向上と訓練
病院におけるサイバーセキュリティ対策には、技術的な対策だけでなく、医療スタッフのセキュリティ意識向上も不可欠です。
多くのサイバー攻撃は、スタッフの不注意や誤操作から発生することが多いため、定期的な教育と訓練を通じてリスクを減らすことが求められます。
例えば、フィッシングメールやマルウェアに関する警戒心を高める研修を実施し、日常業務の中でセキュリティ対策を意識的に取り入れることが重要です。
また、実際の攻撃に近いシナリオを用いた訓練を行うことで、スタッフはどのように迅速に対応すべきかを学び、リアルな状況に備えることができます。
病院においては、スタッフ一人ひとりの意識がセキュリティの強化に直結します。
サイバー攻撃発生時の初動対応体制
サイバー攻撃が発生した際、初動対応がその後の被害を最小限に抑える鍵を握ります。病院においても、攻撃を受けた際に迅速に対応できる体制を整備しておくことが重要です。
まず、攻撃を早期に発見するために、監視ツールや異常検知システムを導入することが不可欠です。攻撃の兆候が確認された段階で、担当チームが直ちに対応を開始し、被害拡大を防ぐための手順を迅速に実行します。
次に、攻撃の影響範囲を特定し、感染が拡大しないようにネットワークの遮断やシステムの隔離を行います。病院では、患者情報や診療データが漏えいするリスクが高いため、情報の保護を最優先事項として対応する必要があります。
病院ができる“備え”とは

病院におけるサイバー攻撃に備えるためには、事前の準備が重要です。セキュリティリスクを把握し、優先順位をつけた対策を実施することで、万が一の攻撃時にも迅速かつ効果的に対応できます。
ここでは、病院が実施すべき「備え」の具体的な方法について解説します。
病院のセキュリティリスクを明確にする脆弱性診断
病院がサイバー攻撃に備えるためには、まずシステムの脆弱性を特定することが重要です。脆弱性診断は、病院のネットワークやシステム、医療機器に潜むセキュリティリスクを洗い出すプロセスです。
これにより、攻撃者に狙われやすい部分を早期に特定し、対応策を講じることができます。定期的な脆弱性診断により、最新のサイバー攻撃に対する耐性を高め、病院のセキュリティ強化を図ることも可能です。
また、外部の専門家に依頼して診断を受けることで、内部だけでは見落としがちなリスクにも対応でき、第三者の視点からの改善策が得られるため、より効果的な対策が可能となります。
自院に合った優先順位の見極め方
病院におけるサイバーセキュリティ対策は、優先順位をつけることが不可欠です。
まず、自院の業務や診療に最も重要なデータやシステムを特定し、リスクの高い部分から対策を進めます。
例えば、患者情報や診療データの保護は最優先です。また、過去のインシデントや脅威情報を参考にし、セキュリティパッチの適用やバックアップ体制の強化を行いましょう。
さらに、自院のセキュリティリスクを明確にするために、三和コムテックの脆弱性診断サービスを利用し、効果的な優先順位を決められます。下記より詳細が確認できます。
参考はこちら
病院を巡る法制度とガイドラインの動向

医療機関のサイバーセキュリティに関する法制度とガイドラインは、急速に進化しています。
特に、医療法施行規則の改正やガイドライン第6.0版の策定など、セキュリティ対策が法的に義務化される方向に進んでいます。本章では、医療機関が遵守すべき法的要件と、最新のセキュリティガイドラインについて解説します。自己点検の推進やチェックリストの活用が今後ますます重要となるでしょう。
医療法施行規則の改正とセキュリティ対策の義務化
2023年、医療法施行規則が改正され、医療機関にはサイバーセキュリティ対策の実施が義務化されました。この改正により、医療機関はセキュリティリスクに対する対策を講じ、情報システムの安全管理を強化することが求められています。
具体的には、医療機関が管理する患者情報や診療データが不正アクセスや漏えいから守られるよう、適切な技術的・組織的対策を講じることが義務化されています。
また、サイバー攻撃による業務の中断や患者への影響を最小限に抑えるため、インシデント発生時の対応体制を整備し、定期的な脆弱性診断と改善を行う必要があります。
ガイドライン第6.0版の主な改定ポイント
2024年に発表された「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」では、医療機関に対してセキュリティリスクの可視化と定期的な脆弱性診断が強調されました。
また、サイバー攻撃が発生した際の初動対応と迅速な措置が重要視され、感染拡大を防ぐための体制整備が求められています。さらに、医療従事者のセキュリティ教育が強化され、内部の意識向上も新たに義務付けられました。
これにより、医療機関はより高度なセキュリティ対策の実施が求められています。
チェックリストの活用による自己点検の推進
医療機関におけるサイバーセキュリティ対策を強化するためには、定期的な自己点検が欠かせません。
ガイドライン第6.0版では、自己点検を効率的に行うためのチェックリストの活用が推奨されています。このチェックリストは、医療機関が抱えるセキュリティリスクを明確化し、優先的に対策を講じるための手助けとなります。
具体的には、情報システムの脆弱性やリスク評価、バックアップの実施状況、従業員のセキュリティ教育など、重要な項目を網羅しています。
定期的にこのチェックリストを使用して点検を行うことで、医療機関はセキュリティの問題点を早期に発見し、迅速な対策を講じることができます。
まとめ
病院を標的としたサイバー攻撃は年々増加しており、医療機関には継続的なセキュリティ対策の強化が求められます。患者の命と情報を守るためには、以下のポイントを中心とした対策が不可欠です。
- 多層防御の構築(入口・内部・出口対策のバランス)
- 従業員への継続的なセキュリティ教育
- インシデント発生時の初動対応体制の整備
- 法制度・業界ガイドラインに基づいた対応
- 定期的な脆弱性診断と自己点検の実施
これらを実行することで、サイバー攻撃に対する組織全体の耐性を高めるとともに、医療サービスの継続性と病院の信頼性の維持につながります。
なお、サイバー攻撃の傾向や手口を理解する上で、IPA(情報処理推進機構)による「情報セキュリティ10大脅威」は有用です。
弊社では、「IPA 10大脅威 2025」をもとに、医療機関向けの解説と対策をまとめた資料をご用意しています。以下よりダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
セキュリティソリューションプロダクトマネージャー OEMメーカーの海外営業として10年間勤務の後、2001年三和コムテックに入社。
新規事業(WEBセキュリティ ビジネス)のきっかけとなる、自動脆弱性診断サービスを立ち上げ(2004年)から一環して、営業・企画面にて参画。 2009年に他の3社と中心になり、たち上げたJCDSC(日本カードセキュリティ協議会 / 会員企業422社)にて運営委員(現在,運営委員長)として活動。PCIDSSや非保持に関するソリューションやベンダー、また関連の審査やコンサル、などの情報に明るく、要件に応じて、弊社コンサルティングサービスにも参加。2021年4月より、業界誌(月刊消費者信用)にてコラム「セキュリティ考現学」を寄稿中。
- トピックス:
- セキュリティ
- 関連トピックス:
- サイバー攻撃対策 基礎知識